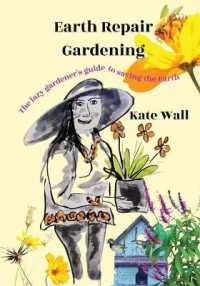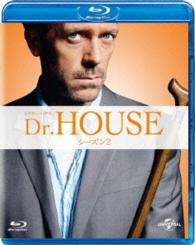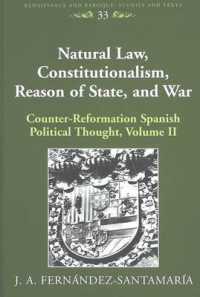内容説明
明治以降、なぜ日本語“僕”は、男性だけに普及したのか?幕末の志士・吉田松陰の書簡から村上春樹の最新長編まで、自称詞に込められた意味を読み解く。
目次
第1章 “僕”という問題
第2章 “僕”の来歴―古代から江戸時代後期まで
第3章 “僕”、連帯を呼びかける―吉田松陰の自称詞と志士活動
第4章 “僕”たちの明治維新―松陰の弟子たちの友情と死
第5章 “僕”の変貌―「エリートの自称詞」から「自由な個人」へ
終章 女性と“僕”―自由を求めて
著者等紹介
友田健太郎[トモダケンタロウ]
1967年、静岡県清水市生まれ。福井県に育つ。歴史研究者。日本語教師。放送大学修士(日本政治思想史)。1991年、東京大学法学部卒業。新聞社勤務後、ニューヨーク州立大学バッファロー校にて経済学修士号を取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tsu55
21
自称詞「僕」を使うことで男性同士の仲間内ではフラットな関係を作れるということまでは、何となく感覚としてわかっていたけれど、ジェンダーニュートラルではないということについては、不覚にもこの本を読むまで気が付かなかった。まぁ僕は、女性が「ぼく」を使ってもいいと思うので、女性のなさんがどんどん「ぼく」を使ってくれれば、男女の間でもフラットな関係を結びやすくなるのではないか。……あのちゃん、がんばってください。2024/02/10
さとうしん
19
中国から伝来した自称詞「僕」が、江戸時代に儒学的な文脈で身分を超えた友愛の絆を示すものとして使われ、松陰ら幕末の志士が同志との連帯を示す自称詞として頻用したことで、明治以後学校教育などを通じて自称詞として普及していく。しかし学生、知識人などエリートが好んだということで軍隊などでは忌避された。また、使用が男性にほぼ限定されるというジェンダー上の限界もあった。それが現代に入り、新たな展開を迎えていく。歴史学、文学だけでなく社会学的な視点も取り入れた総合的な議論になっている点が評価できる。2023/08/04
田沼とのも
16
俺、僕、私、あたし、あたい、小生、余、朕、、、自分のことを指し示す自称詞の種類が日本語には際立って多い。「僕」については、主に男性が使う場面が一般的だが、時々女性が歌う流行歌に「僕」が出てきて気になっていた。浜崎あゆみ、ELT、aiko、鬼束ちひろ、あいみょん、あの、、、、。女性が「僕」を使うと、なぜか愛嬌というか男装の麗人的な性的魅力が醸し出される感があって、それが何に由来するか気になって本著を読んだが、結局はよく分からなかった。こんな研究もあって良いとは思う。2025/10/30
kenitirokikuti
16
「友田健太郎」は著者の本名で、過去には「水牛健太郎」という筆名だったそうな(群像新人文学賞評論部門で優秀作)。著者はNY州立大バッファロー校に留学したので「水牛」なんだろけど、「唐牛(かろうじ)健太郎」もあるよな▲本書の元は修論で、吉田松陰の一人称「僕」を扱ったもの。「僕」は古文であり、和文でも記紀に例がある。しかし、現代日本語の「僕」に直接繋がるのは元禄の頃、儒者が唐代の師道論の引用からだそうな。自分より若く身分の低い者が師であるとき、ある意味で対等な関係になる、みたいなニュアンス。2025/02/23
Ryoichi Ito
10
日本語には自称詞,対称詞が非常に多い。著者はたまたま吉田松陰の手紙を読み,松蔭が〈僕〉を多用していることに気づいた。第3章,第4章は吉田松陰と弟子たちのの〈僕〉に関する著者の修士論文などが元になっている。〈僕〉は古事記にも使われている中国渡来の言葉だ。そこでは目下が目上に向かって使う言葉だった。その後,江戸期に儒教の普及とともに武士や知識階級でも使われるようになった。松蔭とその弟子たちが連帯意識を強調する言葉として〈僕〉を多用した。自称詞が人間関係を表し,また作り変える力を持つことを本書は強調する。 2023/09/04
-
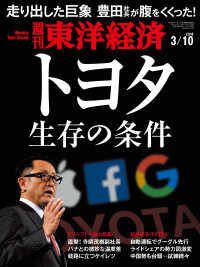
- 電子書籍
- 週刊東洋経済 2018年3月10日号 …