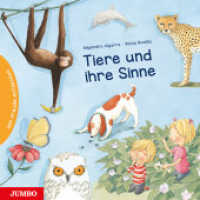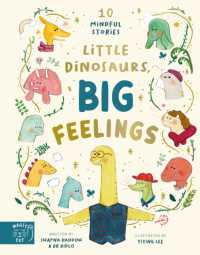出版社内容情報
イベント列車の登場、湘南・軽井沢の観光地化、「ディスカバー・ジャパン」…鉄道と観光、共に発展してきた150年の歴史をたどる。
内容説明
汽笛一声、ニッポン観光時代到来!初詣も松茸狩りも温泉もオリンピックも、鉄道で行こう!鉄道と観光、150年の歴史を描く初の決定版通史。
著者等紹介
老川慶喜[オイカワヨシノブ]
1950年、埼玉県生まれ。立教大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。経済学博士。現在、跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授、立教大学名誉教授。1983年、鉄道史学会設立に参加、理事・評議員・会長などを歴任する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
makoto018
4
鉄道と観光をテーマに明治からの150年の歴史を振り返る。昔、社寺参詣は一生の宿願だったのが鉄道により行楽に変わった。日光、軽井沢、草津などの隆盛には鉄道によるアクセス整備が起爆剤となった。と同時にレジャーの大衆化。鉄道と宅地開発、観光地整備を進めた阪急と東武。鉄道に乗ること自体が楽しみとする観光列車。大学での講義ノートが元のようだけど、体系的にこのテーマでとらえるのが興味深かった。2017/12/14
kentake
3
明治の鉄道黎明期、各地の鉄道経営者は旅客需要喚起の方策の一つとして鉄道を利用した観光振興に力を入れてきた。本書では、その歴史について過去の資料に触れつつ解説されている。現在では首都圏の市街地に取り込まれている観光地の多くが、この時代に開発されたものである点に改めて驚かされる。民鉄の取組みの方が多くの足跡を残しているが、全国的な観光振興という観点からは、国鉄も多くの成果を残していた点が伺え面白い。2017/12/19
tegi
2
要所を深く描くタイプの歴史書。草津、日光、宝塚といった主に私鉄と観光の関わりが多い。戦前戦中の国策と観光のせめぎあいを描く部分が非常に興味深かった。1930年代、満州事変と国連脱退により円貨が暴落した結果外国人観光客が激増する皮肉は、怒涛の円安に翻弄された今年(2022年)からみると非常に苦く感じる。
やまほら
2
鉄道を使った観光について、1章1テーマでまとめたもの。資料豊富だが読みやすい文章で、興味深く読める。8章中7章が戦前の話題で、戦中と戦後は第8章で駆け足で紹介。むしろなくてもよかったんじゃないかな。といいつつ、日中戦争開戦3周年の日の限定で、「一菜主義に則った簡易な弁当」が販売されたというのは印象に残った。2018/04/15
ああああ
1
翌一九三九年一月には、鉄道省運輸局長の山田新十郎が『鉄道時報』に寄稿し、「旅客誘致宣伝については従来の方針を改革し、時局に対応して新たに祖国の認識、敬神崇祖、鍛練を目標とする一つの国民運動を樹立したいと述べた。具体的には青年徒歩旅行に対する運賃割引の期間延長、靖国神社臨時大祭参拝遺族に対する運賃割引・無賃輸送、国民精神総動員健康週間中のハイキング特別割引などを断行する 1982024/01/02