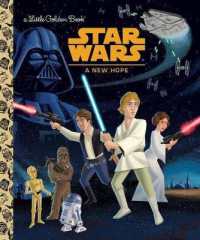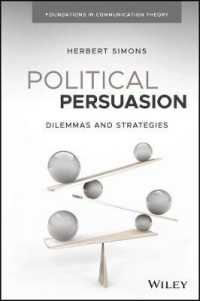- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
小松 和彦[コマツ カズヒコ]
編集
内容説明
妖怪研究は、人間研究である。民俗学の古典のみならず幅広い分野から重要論考を精選、日本文化の多様さ・奥深さを知るテーマ別アンソロジー。
目次
1 総論(妖怪変化の沿革(江馬務)
妖怪(今野圓輔) ほか)
2 妖怪の歴史(付喪神(澁澤龍彦)
妖怪画と博物学(中沢新一) ほか)
3 妖怪の民俗学(女と妖怪(宮田登)
ミカワリバアサンと八日ゾ(岩堀喜美子) ほか)
4 妖怪と現代文化(狸とデモノロジー(柳田國男)
妖怪と現代文化(小松和彦) ほか)
5 妖怪の民俗誌(小豆洗い(清水時顕(中山太郎))
小豆洗いに就て(大野芳宜(柳田國男)) ほか)
著者等紹介
小松和彦[コマツカズヒコ]
1947年、東京都生まれ。国際日本文化研究センター名誉教授。専門は文化人類学、民俗学。長年、日本の怪異・妖怪文化研究を牽引してきた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
68
本シリーズの他の巻は「鬼」や「河童」等と割とイメージしやすい物が多いのであるが、本書は題材が「妖怪」というだけあり、その名通り全体的にどこか漠として掴みがたい。妖怪の全体像に触れたのは冒頭の「総論」だけで、後は付喪神や小豆とぎ、首無し馬や舟幽霊といった個々の妖怪について書かれた論文ばかり。これはこれでどれも面白いものばかりだけど、やはりこのような細部を見つめているとやはり全体像がどこかぼやけて見えてしまう。そのぼやけ具合が何となく妖怪に相応しいような…。その意味で本シリーズを代表するような一冊でした。2022/11/13
佐倉
13
撲滅するべき対象という井上円了の立場や神から零落したものという柳田以来の古い妖怪観を反映した井之口論文など退屈する部分もあったが、川崎市の民俗を記録した『ミカワリバアサンと八日ゾ』岩堀喜美子など各地方の細かい事例を見るものやトイレから出る手や口裂け女のような現代妖怪をリアルタイムで捉える『子どもと妖怪』常光徹『話の行方』野村純一、妖怪という近代的な語彙を近世期の人々の見方に沿って理解しようとする『妖怪画と博物学』中沢新一『芝居と俗信』横山泰子のような論文まで様々。2025/01/06
らむだ
4
シリーズ二作目。Ⅰ:総論で大枠を示す。Ⅱ:付喪神から化物尽までの妖怪の歴史を外観。続くⅢ・Ⅳ・Ⅴで具体的な妖怪の話を過去から現代、東から西へと展開していく。2023/06/18
-

- 洋書
- Going Home