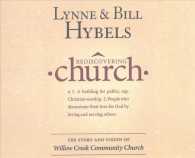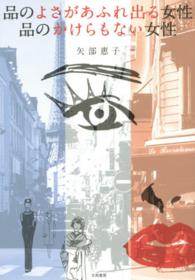- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
分け入っても分け入っても謎?世界の不思議に体当たり。呪術、精霊、悪魔、鬼…文化人類学者が体験した怪異。
目次
1 ベナンの妖術師(村津蘭)ベナン
2 ヒマラヤの雪男イエティ(古川不可知)ネパール(クンブ地方)
3 どうして「呪われた」と思ってしまうの?―現代ロシアの呪術信仰(藤原潤子)ロシア
4 かもしれない、かもしれない…(近藤宏)パナマ東部(中南米)
5 ヴァヌアツで魔女に取り憑かれる(福井栄二郎)ヴァヌアツ(アネイチュム島)
6 中央オーストラリアの人喰いマムー(平野智佳子)オーストラリア(中央部)
7 幼児の死、呪詛と猫殺しと夢見(奥野克巳)ボルネオ島(東南アジア島しょ部)
8 鬼のいる世界(川口幸大)中国(広東省)
9 映像によって怪異な他者と世界を共有する方法―ジャン・ルーシュの民族誌映画が啓く新しい道(イリナ・グリゴレ)日本
著者等紹介
奥野克巳[オクノカツミ]
文化人類学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モモ
38
9人の文化人類学者たちが体験・見聞した怪異。「ペナンの妖術師」自分の価値観から遠いと思っていたが、妖術が人々の行動を良い方向に導く力があるのが意外で新鮮な驚きをもつ。「ヒマラヤの雪男イエティ」ヒマラヤでは幽霊が現れやすいのが日の出や夜の12時。国によって現れやすい時間があるのだろうか?ロシアでは「言葉は物質化する」なのでネガティブなことは言ってはいけない。でも、うっかり言ってしまった時は、机など木でできた物を、コンコンコンと3回たたけば良いそう。日本での言霊と似ている。いろいろと興味深い一冊でした。2024/06/14
くさてる
29
9人の文化人類学者による世界各地の怪異紹介。まったくしらない外国の怪異、というけれど、日本にある怪異と同じように思うものもあれば、まったく分からないような断絶を感じるものもあって、面白かった。怪異は人間の生活や文化と切り離せないものなんだと思う。それぞれの学者の方の文章に誠実さがあって、良かったです。2024/06/30
chiaki
29
9人の文化人類学者たちが自ら調査研究してきた土地で出会った怪異的な現象や体験を集めた1冊。土地土地で呪術信仰のあり方や、精霊や悪魔などに対する考え方には違いがあって、その怪異の多様さが面白い。例えば、中国人の捉える鬼(死を強く連想させるもので人間の連続性の上にある。)と日本それとの違いが興味深かった。人間、いろんな偶然や説明のつかないものに抱く恐怖を"呪いのせい"にすることで納得を得てるんだな。ヴァヌアツで魔女に憑かれた教授が、現地文化を垣間見るチャンスと捉える変人めいた所が妙にツボでした。2024/06/25
メタボン
22
☆☆☆☆ 怪異も文化や宗教によって様々だと知って興味深かった。何かわからないことを妖術によって納得させるベナン(日本の厄払いのような文化)。雪男イエティを観光に生かすネパール。何でも呪いと結びつけるロシアでは呪術師の存在が大きい。パナマの川の悪霊アントミャ。オーストラリアの人喰いマムー。ボルネオ島カリスでは、我が子の病気をシャーマンの儀礼によりカタベアアンという精霊の仕業だと納得させようとする母の姿を見る(本編で一番怪異の神髄を捉えていると感じた)。イリナグリゴレが紹介するジャン・ルーシュの民俗誌映画。2025/08/16
佐倉
22
アフリカの妖術師、ロシアや東南アジアのの呪術や呪詛、ヒマラヤのイエティ、南太平洋の魔女。世界の様々な地域における呪いや妖怪といった“怪異”をそれぞれのフィールドワーカーたちの実体験によって紹介していく。意志や行動など本当はコントロール不可能な物事を妖術に仮託するベナンの事例、ボルネオ島での幼児の死について真実を知る人がいながらそれを大っぴらに語らずに精霊の物語に回収したケースなど、恐れや悲しみや禍根をひとつのコミュニティ内に残さず円滑に回すシステムとしての呪術や妖術の事例が興味深い。2025/07/17
-

- 電子書籍
- 顔を上げて月を見て!【タテヨミ】第48…