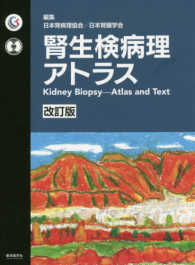内容説明
あらゆる領域に巨大な影響を与えたフーコーの最も重要な著作を気鋭が四十二年ぶりに新訳。フーコーが『狂気の歴史』『臨床医学の誕生』『言葉と物』を生み出した自らの方法論を、伝統的な「思想史」と訣別し、歴史の連続性と人間学的思考から解き放たれた「考古学」として開示する。それまでの思考のありかたに根底から転換をせまる名著が新たなすがたで甦る。
目次
1 序論
2 言説の規則性(言説の統一性;言説形成 ほか)
3 言表とアルシーヴ(言表を定義すること;言表機能 ほか)
4 考古学的記述(考古学と思想史;独創的なものと規則的なもの ほか)
5 結論
著者等紹介
フーコー,ミシェル[フーコー,ミシェル][Foucault,Michel]
1926‐1984年。20世紀後半における最も重要な思想家
慎改康之[シンカイヤスユキ]
1966年生まれ。明治学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
30
自分の足元を掘り崩し、その岩を使ってどんづまりの岬の突端から「向こう岸」へと渡って見せたアクロバティックが「言葉と物」までの3作品だとすれば、この本は、その曲芸で何をやったのか、何をやらなかったのかを縷々書き尽くすことで、それが再現可能であること、いやそもそも向こう岸なるものが存在することを証したものだろう。◇特に前半は難解だが、それは、科学も主体も人間も実体じゃなく仮初という西洋近代を揺るがす苦しみが、元来無常の伝統を持つ僕らには想像がつきにくいからかも。だからそこを率直に語る最終節はすっと入ってくる。2015/04/16
マウリツィウス
18
【MICHEL/FOUCAULT】「知の考古学」の冠した仏語表記基準は連環史において成立する幻想暦を実質意味し発掘の美学はむしろ原典引用に生かされる。古典神話論創設基準が誤読される文明を疎ましく思うフーコーは異端者を援用したカバラ記号論を実質言説より取去る。系譜にあるショーレム残影は神秘主義大系ではなく原則倫理に用いられ、根底と改変は知に属する心理学見地を発揮するも考古と現代の二重成立を束ねた功績価値を吟味すると悪夢幻想とは異教起源ではなくキリスト誤読に由来する。丹念と検証は極め、ゴダール幻想は反証論済。2013/05/28
ハチアカデミー
16
知のアウラをぶっ飛ばせ! フーコー先生のアジテーショナルな一冊である。特定のモニュメント(事件)とそれに付随するドキュメント(報告)という形ではなく、雑多なドキュメント(テクスト)の中からモニュメント(主題)を導き出すこと。話者であれ書き手であれ、その言葉の背後に多くの歴史を内包しており、同じ言葉でもどんな状況で発したものであるのかによって指示内容も変わる。知の考古学とは、特定の言説を御神託のように崇めるのではなく、言説を集合体(アルシーブ)とみなし、それが立ち現れるシステムを探る試みなのであろう。2013/07/08
Ecriture
14
歴史の連続性と主体の至上権を放棄した言説形成分析、「考古学」についての著。言説は間断なき直線状の歴史を辿って一つの根源に辿り着けるものではなく、まして一人の人間のもとに還元できるものでもない。「医学なるもの」、「文法なるもの」、「政治経済学なるもの」が諸関係の束の内でのオペレーションによって自身を変化・形成(言説形成)していく、まさにその内での分析は超越論的観測点を手放すことにつながる。言説の散乱と分裂を、主体と言説の共同存在(ともにあること)論・多元的実存を。2013/01/27
さきん
12
はっきり言って良くわからなかった。眠たくなった。キーワードは言述、言表だと思う。要再読ではある。誰か解説しているのを読みたい。2015/08/18