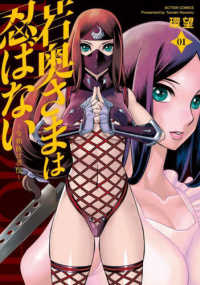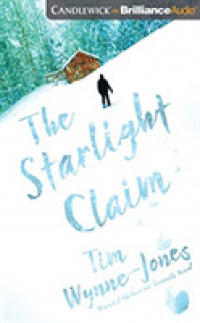内容説明
コーモ湖畔に住む若者レンツォは、いいなづけルチーアと結婚式を挙げようとするが、村の司祭が突然、式の立ち会いを拒む。臆病な司祭は、美しいルチーアに横恋慕した領主に、式を挙げれば命はないとおどされたのだ。二人は密かに村を脱出。恋人たちの苦難に満ちた逃避行の行く末は―ダンテ『神曲』と並ぶイタリア文学の最高峰。読売文学賞・日本翻訳出版文化賞受賞作。
著者等紹介
マンゾーニ,アレッサンドロ[マンゾーニ,アレッサンドロ][Manzoni,Alessandro]
1785‐1873年。19世紀イタリア最大の国民作家。ミラーノの貴族出身。1860年上院議員となり、イタリア統一の精神的指導者として国民的尊敬を受けた
平川祐弘[ヒラカワスケヒロ]
1931年東京生まれ。東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
169
イタリアでは「神曲」と並んで国民文学の位置付け。古事記や日本書紀が「聖書」とすれば、「こころ」と「人間失格」が「神曲」と「いいなづけ」にあたるのだろうか。高校生はみな読むそうだから。北イタリアの言葉をこの小説でまとめており、イタリア語史的にも重要。1500年末のイタリア。司祭が、娘の方を気に入った領主の脅しに簡単に屈し、若い男女の結婚を取り仕切るのをやめる。ロミオとジュリエットの国(作者はイギリスだが)だと思うも、悲劇ではないようでドタバタが続く。結婚は神の下で、教会で執り行わねばならないのが曲者だ。2017/03/17
まふ
119
「イタリアの漱石」的大作家とされるマンゾーニの初読。時代は1628年、場所はミラノ公爵領のレッコという集落。普通の平民のカップルなのにルチーアがイカレタ領主のロドリーゴに横恋慕されて結婚を不許可とされる。義憤に燃えたクリストフォーロ修道士が何とか二人を応援するが領主の策謀によって本人自身が転勤させられる。一方の青年レンツォは村の騒動に巻き込まれて追われる身となる…。物語は至って単純なスジだが、的確な文章により面白く読める。訳者の平川氏の解説が行届いているので分かりやすい。後半が楽しみである。⇒2025/01/04
のっち♬
106
舞台は十七世紀前半のイタリア北部。領主の横恋慕によりルチーアとの結婚を妨害されたレンツォは彼女の母を加えた三人で村を脱出して母娘を修道院に匿い、ミラーノへ向かう。臆病者の司祭やお喋りな下女など序盤からいきいきとした人物描写が冴え渡っており、ウィットに富んだ比喩やコミカルな場面も交えておおらかな空気が支配する。しかし、それは後半へ進むにつれて次第に暗転していく。苦痛と動揺に満ちた「哀れな聖女」の過去は、それだけでも充実した読み物になっている。パン屋の暴動の場面も民衆の奔流や叫喚が迫ってくるような臨場感だ。2021/02/28
翔亀
38
【コロナ43-1】騙されたつもりで読んでみたが、こんなに面白く夢中になってしまうとは思わなかった。心に残る小説となった。■初めて名を聞く作家と作品。ペストを題材にしている小説ということだけで手にした。まず巻末の解説を読む。訳者の平川祐弘は、日本では知られていないがイタリアの夏目漱石、国民的作家だとし、丸谷才一が「われわれの眼前にイタリアの社会がそそり立つ」と絶賛、ホフマンスタール(R.シュトラウスのオペラの台本の人ですね)がイタリアで最も有名で「イタリアの心だった」、と郷土愛から生まれた芸術作品としては↓2020/08/10
かごむし
25
時代というものが凝縮されたかのような読み応えがあるのに、めちゃくちゃ読みやすくて面白い。高度に洗練されたハラハラドキドキの物語。原作の力ももちろんあると思うけど、訳も素晴らしい。なんと注が1個もない。200年前に書かれたイタリアの物語に、注が必要ないわけがないのだが、翻訳作品の壁を感じさせないほど、訳がこなれている。日本では有名でなく、僕も自分の読書リストで見るまでは存在すら知らなかったけど、人の目の届かぬところに埋もれていて、もっと紹介してほしいのにと悔しい気分になる。というわけで中巻へ。楽しみである。2018/03/22