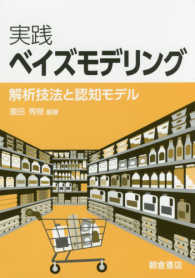出版社内容情報
天神さまとして現在も知られる菅原道真。その恩義を受けた三つ子、梅王丸・松王丸・桜丸がそれぞれの主君への忠義とのあいだで葛藤する。書道の奥義の伝授、親子の愛憎、そして寺子屋の悲劇…。社会の矛盾や理不尽を緻密な構成で描いた人間ドラマ。歌舞伎や文楽でいまも愛される名作浄瑠璃を血の通った名訳で。
目次
初段(大内の段;加茂堤の段;筆法伝授の段;築地の段)
二段目(道行詞の甘替;汐待ちの段;道明寺の段)
三段目(車曳の段;佐太村の段)
四段目(筑紫配所の段;北嵯峨隠れ家の段;寺子屋の段)
五段目(再び、大内の段)
内容説明
天神さまとして現在も知られる菅原道真。その恩義を受けた三つ子、梅王丸・松王丸・桜丸がそれぞれの主君への忠義とのあいだで葛藤する。書道の奥義の伝授、親子の愛憎、そして寺子屋の悲劇…。社会の矛盾や理不尽を緻密な構成で描いた人間ドラマ。歌舞伎や文楽でいまも愛される名作浄瑠璃を血の通った名訳で。
目次
初段(大内の段;加茂堤の段;筆法伝授の段;築地の段)
二段目(道行詞の甘替;汐待ちの段;道明寺の段)
三段目(車曳の段;佐太村の段)
四段目(筑紫配所の段;北嵯峨隠れ家の段;寺子屋の段)
五段目(再び、大内の段)
著者等紹介
三浦しをん[ミウラシヲン]
1976年東京生まれ。小説家。2000年『格闘する者に○』でデビュー。06年『まほろ駅前多田便利軒』で直木賞、12年『舟を編む』で本屋大賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ポチ
41
しをんさんらしい現代語訳の浄瑠璃。菅原道真が貶められ雷神となるまでを恩や忠義、情、人の心の醜さなどを交え一気に読ませてくれました。2024/12/29
ちえ
39
来月母と行く歌舞伎の予習。三浦しをんさんの訳はぶっとんだ部分もあるけれどこれなら楽しんで読めるわ。以前文楽と歌舞伎でも有名な寺子屋や車引きは観ているけれど、こうやって全体を読むと『菅原伝授手習鑑』という題名の意味もよく分かるし、今でも菅原道真が昔から人びとに親しまれていたのが伝わってくる。最後の大内の段はめちゃめちゃ面白いの、それなのになかなか観る機会が無いのは残念だなぁ。2025/08/21
マホカンタ
29
文楽でも歌舞伎でも観たことのない『菅原伝授手習鑑』。だけど、しをんさんが訳すというなら読まないわけにはいかないでしょうと手に取ってみた。菅原道真が天神さまと崇められるまでのいきさつを描いているのだが、訳ならしをん節は控え目か?という思いはよい意味で期待を裏切られます。だって、きっと他の人なら『ガバチョ!と恋のアクロバット』とか、『誤認逮捕しようとしちゃった、ごめんね』なんて訳してないはず(笑)。この訳で是非とも義太夫節を聞きたいのですが、それなら間違いなく文楽を観に劇場いくのですが、無理ですか?2025/07/13
ヨーイチ
27
河出文庫・古典新訳コレクション31とある。浄瑠璃の元本は学生時代に一応読了。新米の歌舞伎ファンとして頑張って入手した物。残念ながら文楽は未聴。筋は知ってたけど、改めて「新訳」に触れて印象、解釈が鮮明になった。ありがたいことだ。ご存知の通り歌舞伎公演では「寺子屋」とか一場面だけ上演されることが多いので、登場人物の背景などは(これがまた入り組んでいることが多い)置き去りにされることがある。でも歌舞伎でも文楽でも表現者の大元は「原作」にある筈で知っておいた方が良い。少し視点を変える。続く2025/10/24
びぃごろ
17
「日本文学全集10」から抜粋され文庫化される。池澤夏樹編集のこの全集、出た順に読むぞと思っていたが、未だ2冊しか完読出来ていない…あの厚い本も文庫として一つずつバラけると手にはしやすいが、「読んだー!」という達成感は薄れるなぁ(笑) 通しでもなかなか上演のない四段目「天拝山」「北嵯峨」五段目は文楽で観たいものだ。国立劇場を改修するまで開放できないものか…しをんの口語訳は楽しい。文庫版あとがきもあり。人格不統一よりも藤原時平がトキヒラとルビがあったり、シヘイと読ませたりする方が気になったよぅ。2025/01/25
-
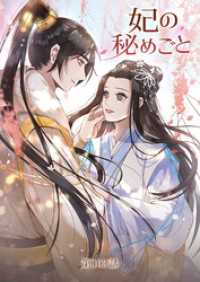
- 電子書籍
- 妃の秘めごと【タテヨミ】 103話