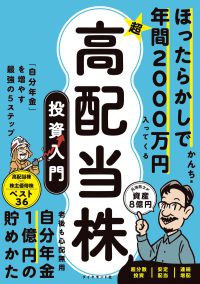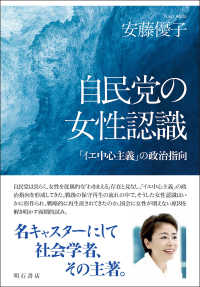内容説明
二〇世紀フランスを代表する作家と自らを重ね合わせながら紡ぐ魂の二重奏。ヨーロッパの建築や美術をめぐる思索の軌跡、出会った人々の思い出。「なによりもまず私をなぐさめてくれる島」として須賀が愛したヴェネツィアの記憶。画期的論考「古いハスのタネ」他18篇。
目次
ユルスナールの靴(フランドルの海;一九二九年 ほか)
時のかけらたち(リヴィアの夢―パンテオン;ヴェネツィアの悲しみ ほか)
地図のない道(地図のない道;ザッテレの河岸で)
エッセイ/1993~1996(塩一トンの読書;七年目のチーズ;屋根裏部屋と地下の部屋で;白い本棚;ピノッキオたち;太陽を追った正月;となり町の山車のように;マドモアゼル・ヴェ;リペッタ通りの名もない牛乳屋;大洗濯の日;思い出せなかった話;街路樹の下のキオスク;ヤマモトさんの送別会;古いハスのタネ;なんともちぐはぐな贈り物;クロスワード・パズルでねむれない;古いイタリアの料理書;ユルスナールの小さな白い家)
著者等紹介
須賀敦子[スガアツコ]
1929‐98年。兵庫県生まれ。聖心女子大学卒業。上智大学比較文化学部教授。1991年、『ミラノ霧の風景』で女流文学賞、講談社エッセイ賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
79
今回も全集修行である。今回でエッセイは終わりになる。エッセイの感想としては品やな文章と知性を兼ね備えているのに読者を置いていかない優しさもあった!そのエッセイの中でも塩1トンの読書がとても印象にのこっている。じつはこのお話は須賀敦子さんの本でもうすでに読んだことがあった。でも再度読んでも素晴らしいとかんじる。人を知るには塩1トンお互いに舐め合うくらい時間がかかる。それは古典も同様である。時間をかけて理解する必要がある。この本もまた時間をかけて理解したいと思える作品であった!また読みたくなった!2023/03/03
佐島楓
72
須賀さんが吉行淳之介を読んでいらしたところに、意外を感じた。なんとなく対極にいる作家のように思っていたが、病すれすれの退廃的なところに惹かれたとしたら、わからなくもない。2018/09/03
U
38
『ユルスナールの靴』を読了。ユルスナールの生涯と自身を重ね合わせるかたちで綴られた須賀敦子晩年の作。「だれの周囲にも、たぶん、名は以前から耳にしていても、じっさいには読む機会にめぐりあうことなく、歳月がすぎるといった作家や作品はたくさんあるだろう。」須賀敦子にとってユルスナールがその人物のひとりで、作品を愉しみ、著者に興味をもつ、という単純な思いのみが、本作を書かせた理由だったという。すきな章は、友人ようちゃんが登場する「一九二九年」と、ユルスナール晩年の居マウント・デザート島の来訪話「小さな白い家」。2015/07/29
U
29
「塩一トンの読書」を朝の電車で再読。「ひとりの人を理解するまでには、すくなくも、一トンの塩をいっしょに舐めなければだめなのよ」須賀さんのお姑さんのことばから始まるこのお話は、わたしのお気に入り。一トンの塩をいっしょに舐めるというのは、喜怒哀楽をいっしょに味わうという意味で、一トンを舐めつくすには気の遠くなるような時間がかかる。人間や書物も、それだけ理解しつくせないものだ、ということなのですが、このお話をよむと、忙しさや結果主義に流されずに、過程こそ大事にしながら、限りあるときを過ごさなきゃと思えるのです。2015/08/20
おにく
26
全集第3巻は執筆活動後期のエッセイを収録。これまでエッセイを通して、自分の人生を見つめ直して来た須賀さんが、次のステージへシフトしようとしていた時期だと思います。この本に収録されている"ユルスナールの靴"は、女性作家マルグリット・ユルスナールの軌跡を紹介したエッセイ集。ユルスナールがアメリカに旅行中、戦争が本格化し、何年も自国に帰れなくなるという状況から、長年温めてきた長編小説を書き上げる辺りは、須賀さんが書こうとしていた長編小説のインスピレーションにつながったのではないでしょうか?(つづく↓) 2020/06/19