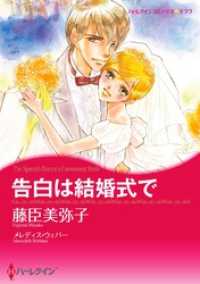内容説明
1977年、著者はヘブライ語を学ぶため、ユダヤ人の夫と共にイスラエルの語学学校へ。同級生は各国から集まった八歳~七〇歳の生徒たち。未知の風土、生活、食べ物、そして歴史に向き合い、「他者を語る」ことに挑んだ、自由で真摯な旅の記録。多くの書き手に影響を与えた翻訳者の初めてのエッセイ集。
目次
砂漠の教室
イスラエル・スケッチ1
ヨセフの娘たち
イスラエル・スケッチ2
なぜヘブライ語だったのか
おぼえ書きのようなもの
解説 思考と身体を外に開く(平松洋子)
著者等紹介
藤本和子[フジモトカズコ]
1939年生まれ。早稲田大学卒業後、1967年に渡米。その後、数多くのアメリカ文学の翻訳を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buchipanda3
100
エッセイは著者がヘブライ語を学ぶためにイスラエルの語学教室に入る所から始まる。半世紀前のとは言え、未知の国の人々の感性に触れる話を興味深く読めた。入学早々、帰りたいなど文句が吐かれるが、ざっくばらんな文章が何か良い。教室は国内外のユダヤ人が多く、それはヘブライ語が今のユダヤ人にとって特別だから。またユダヤ人と言っても出自の違い(西欧と東洋)があり単に一括りに出来ない。読み進めると著者がヘブライ語を学ぼうとした本当の理由が語られ、自分と異なる視座に対して表面的ではない深い理解を試みる気概ぶりに感銘を受けた。2023/08/26
どんぐり
88
パレスチナ人作家カナファーニーがレバノンで暗殺された5年後の1977年、日本人の藤本和子はヘブライ語を学ぶためにイスラエルの語学学校へ留学。「なぜヘブライ語などを学ぶのか」ときかれた藤本は、「わたしが個人としてユダヤ人やユダヤ主義の思想に触れ、それについてある一定の責任を引き受けようとしたこともむろんある」と書いている。そして、砂漠の教室を卒業して、イスラエル人の夫とともにハイファに住んでいた頃に、「差別とか偏見とか迫害とかいう手軽な常套語では、ユダヤ人が傷ついた人びとであることを満足に説明することは→2024/07/09
A.T
25
2000年も昔にアラブ人に追い出され、その地へ戻ってきたユダヤ人のことを1970年代に描いたエッセイ集。当時、ヨーロッパなど西洋からイスラエルへ戻ったのは全体の40%程度で、残りのインド系、中東系有色人のユダヤ人へ差別があったこと。欧州からの差別によってパレスチナへ来たのにも関わらず、白人系ユダヤ人は元の欧州の、しかもゲットー仕込みの文化を捨てられずにいたという。ならば、現在のアラブ人たるパレスチナ人への反感は当然であったろうし、融和ははじめから無理だったのかとも想像してしまう…2025/05/10
ケイティ
22
ヘブライ語を学ぶためにイスラエルに留学したエッセイだが、まさか1970年代の話だとは。いい意味で、外に出すために整えた体裁でなく、彼女の気持ちや主張がそのままカラっと綴られていて面白い。言語を学ぶとはその国そのもの、歴史や文化に包括的に理解するきっかけとなる。同時に、言葉をもって言語を語ることの難しさにも向き合わざるを得ない。イスラエルとユダヤ人の複雑さなど、多面的に思考を巡らせる情熱的な姿勢に、もっと世界のことを知らなくてはと痛感しました。いわゆるエッセイ以上に読み応えのある一冊。2023/09/22
tyfk
8
「……わたしはたいして謙虚な人間ではないのだから。ただ、おまえはいかなるものの名において、このようなことを書くのか、としつこくたずねるなにかがある。「シッ!」といってやるのだが、そいつはどかない。そんなに不安なら、本など出すのはやめるべきだ。ところがやめもしないのである。やめないが、身のおきどころもないのである。」2023/08/05