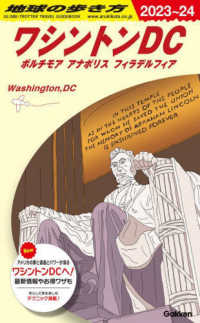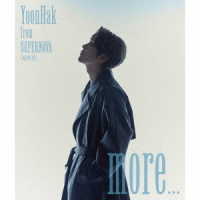内容説明
妻子の体が半分にやせ細り死ぬ家、出所したばかりの犯罪者と相部屋になった男の恐怖体験…身の毛もよだつ怖い話から、尻子玉を奪い合う河童やのっぺらぼうなど昔ながらの怪談まで収録。新旧怪談の中から種村季弘が選りすぐった日本怪談アンソロジー!
著者等紹介
種村季弘[タネムラスエヒロ]
1933‐2004。ドイツ文学者、翻訳家、エッセイスト。『ビンゲンのヒルデガルトの世界』で芸術選奨、著作集「種村季弘のネオ・ラビリントス」で泉鏡花文学賞を受賞。多くの著書、マゾッホ、パニッツァ、ホフマンなどの翻訳で知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sin
80
〈家〉丈吉、春夫の悪意を練り上げたる霊の捏造に反し、健一は家に憑くモノと共存し風情ある佇まいを醸す。筒井は格別。淳之介はタブーを記し、鴎外は高等遊民のごとくうだうだと考察す。足穂は《稲生物怪録》〈坂〉百閒の幻想。八雲の良品。鴎外、昇平は奇しくも戦時の日本の大陸に於ける強姦殺人を語りその形同じくして事実と知れる。〈沼〉与志雄の幻談。露伴蘊蓄多し。葦平河童劇。仁二郎鯉の情念。〈場所〉左保或いは再現か?道夫は小噺。百合子生きることは怪。信男赤マント考。半村は宿モノで絶品、鏡花雪中無謀。龍彦病膏肓に入るを語る。2021/07/20
mii22.
70
不思議な話であったり、気味の悪い話であったり、ぞっとするような震え上がるような怖さはないが日本らしい薄暗く湿度の高い怪奇譚。一番怖かったのは筒井康隆/母子像、好みの話は吉行淳之介/出口と泉鏡花/雪霊続記、淫靡な感じの小田仁二郎/鯉の巴も強烈な印象を残す。家、坂、沼…嫌な感じで近よりたくないのに何故か気になる場所や幽霊がよく現れそうな川や橋や旅館など、誰にでも近寄りがたいけど気になる奇妙な場所があるはず。そこでは自分の妄想が恐怖となって姿を現すことだってあるのかも。2020/08/25
HANA
66
名アンソロジーの復刊。上巻には家や坂等の場所に関する作品中心にまとめられている。鴎外、鏡花といった大家から刊行時の新人まで、幽霊屋敷からメタな作品まで、収められている範囲は幅広い。アンソロジーだけあり何度も読み返した作品も多め。筒井や百鬼園先生、足穂に八雲等は何度読み返してもその薄気味悪さやノスタルジアに絡み取られるような心地がするし、初めて読む作品「鯉の巴」はお約束とエロティシズムに「わたしの赤マント」は都市伝説という題材と構成に舌を巻く。怪談は文芸の至極であるという事を思い出させてくれる一冊であった。2019/08/09
Kouro-hou
37
種村季弘のアンソロジーの復刻版。買ってみて上下巻の上だった事に気づく。どこかに上巻って書いて欲しいw 家や坂などそれぞれ場所がテーマの作品が集う珍しいセレクトで楽しい。(霊や身体は下巻) 森鴎外や泉鏡花などの文豪や筒井康隆、笹沢佐保のメジャーどころ多数。怪談とはただコワイ話をすればいいわけではないとか表現、構成の技術など短篇ならでは技巧も楽しめる。意外と学校の読書感想文に向いてそうと思ったりも。お気に入りは油断して正体さらすのが愛らしいw日影丈吉「ひこばえ」、最後の投げっぱなしが笑えて怖い「終の岩屋」。2020/01/15
くさてる
31
昔ながらの怪談から昭和の作家の恐怖小説まで、選りすぐりのアンソロジー。既読のものでは、やはり筒井康隆「母子像」豊島与志雄「沼のほとり」都筑道夫「怪談作法」などが良かった。初読では圧倒的に半村良「終の岩屋」がすごい。なにこれ。デラメアの「謎」を連想しました。他にも面白いものが多く、良いアンソロジーでした。2020/12/06