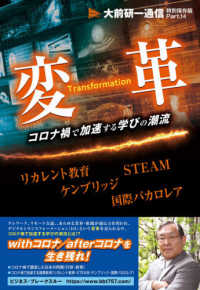出版社内容情報
戦中に19歳で拝命してから半世紀、激動の時代に「祈り」続けた著者が、数奇な生涯とベールに包まれた「宮中祭祀」の日々をつづる。
高谷 朝子[タカヤ アサコ]
1924年滋賀県大津市生まれ。1943年に内掌典を拝命し、以後半世紀にわたって奉仕する。2000年に勲四等瑞宝章を受章。2001年に退職。交替制が定着した現在、生涯をかけて伝統を継承した最後の存在。
内容説明
内掌典と呼ばれる人たちがいる。皇室の祭祀を内から支えてきた未婚の女性たちだ。その伝統は古代から口伝でのみ受け継がれ、今も宮中三殿で起居する内掌典によって護り続けられている。そんな神秘に満ちた皇居の奥で半世紀以上にわたり奉仕し続け、激動の時代を見てきた著者が明かす、自らの生涯と宮中祭祀の日々とは?
目次
上がりましてからのこと
内掌典の御用
次清のこと
お正月の御用
お正月の御神饌
節分からの御用と候所の行事
六月からの御用
着物のこと
内掌典の重儀
戦中戦後のこと
昭和天皇・皇后両陛下の思い出
御大礼
今上陛下・皇后陛下のこと
賢所の式
賢所を下がって
著者等紹介
高谷朝子[タカヤアサコ]
元内掌典。1924年滋賀県大津市生まれ。1943年、戦況が悪化する中で内掌典を拝命。以後半世紀にわたって宮中祭祀に奉仕する。2000年に勲四等瑞宝章を受章。2001年に退官。交替制が定着した現在、生涯をかけて伝統を継承した最後の存在。千葉県内で静かに余生をおくる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
syaori
おかむら
やじ
baba
-

- 電子書籍
- 大学ではじめて恋人ができた人の話 スト…
-
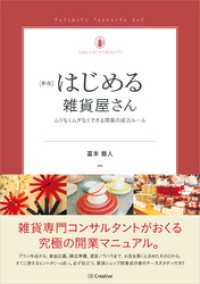
- 電子書籍
- 新版 はじめる雑貨屋さん ムリなくムダ…