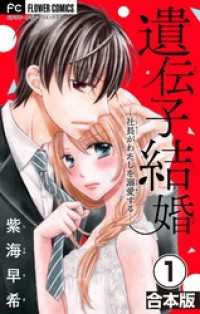出版社内容情報
周辺国の手からハプスブルク帝国を守り抜き、16人もの子をなした、まさに国母。波乱と情熱に満ちた生涯を描く。
【著者紹介】
1941-005年。元東洋大学教授。著書に『ハプスブルク家』『ハプスブルク家の女たち』『カール五世』『フランツ・ヨーゼフ』『ハプスブルク夜話』などがある。
内容説明
生きた、愛した、戦った―。プロイセンをはじめ、ハプスブルクを狙う周辺国から女手ひとつで帝国を守り抜き、自らも十六人の子をなした、まさに国母。波乱のなかでも、常に慈愛に満ちた行動を忘れなかった、「テレーゼ」の美しき生涯を描く、ハプスブルク研究第一人者による傑作評伝が待望の復刊。
目次
第1部 若き女王(王女誕生;フランツ・シュテファン・フォン・ロートリンゲン ほか)
第2部 七年戦争(フランツ、皇帝になる;ハウクヴィッツ ほか)
第3部 母としてのマリア・テレジア(シェーンブルン;フランツ ほか)
第4部 晩年の女帝(フランツ帝、インスブルックで薨去;ヨーゼフとの確執 ほか)
著者等紹介
江村洋[エムラヒロシ]
1941年、東京生まれ。1970年、東京大学大学院比較文学比較文化博士課程修了。元東洋大学教授。ヨーロッパ文化史、特にハプスブルク家を研究。2005年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まりお
35
マリア・テレジア。オーストリア、ハプスブルク家が産み出した女帝。蝶よ花よと育てられ、父が亡くなってからは女傑と変身。女と侮ったプロイセン達が襲い来る中、女傑に更に磨きがかかる。まさに、熾烈な争いから産まれた女傑であった。それ故、夫フランツとの馴初めや夫婦生活、子育て、国民を愛するエピソードが暖かい。2019/12/01
ぱなま(さなぎ)
23
マリア・テレジアの政治的手腕の発揮について知ることができ興味深かった。晩年息子に皇帝の座を譲ってから実権をすっかり失ってしまうくだりには少々考えさせられるものがある。たとえば新しい世代の人間は上の人間が過去のやり方に固執することに苛立つことがままあるけれど、上の世代には上の世代なりの意図があって、大局的にみればあえて時勢に沿わない道の方がより良いという可能性も考えてみる価値があるかもしれないのだ。とはいえ旧習にこだわることが良いとも思えないのだが、公平な目で世界をみるのはなんと難しいことだろうか。2018/09/18
こぽぞう☆
13
旅のお供として持ち歩き、帰ってきて読了。マリア・テレジア、昔から好きだったけど、うん、素晴らしい。系図や地図、図版がおそまつだったのが残念。2019/12/06
ゆずこまめ
8
あの大帝国を見事に治めただけでもすごいのに、16人子供を産みながらっていうのが超人的。男にならなくても政治はできる。スケールもレベルも違いすぎるけど、ちょっと勇気わきます。2014/12/04
鐵太郎
6
マリア・テレジアは基本的に平和を愛するひとだった、と著者は言います。伝えられるその紀伝によっても、その認識は間違いではなさそう。しかし同時に、政治・軍事・行政に関する「帝王教育」を受けなかったにもかかわらず、平和はそれを断固たる意志と不断の警戒、そして充分な軍備によって維持できるもの、という当時の世相を正確に理解していたのでした。こうして描かれた彼女ですが、江村さんの筆致は、優しいね。年を取るにつれて頑迷固陋の老害化していった(といわざるを得ない)マリア・テレジアを、最後まで優しく描きます。2014/05/12