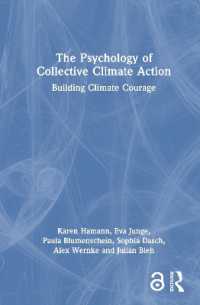内容説明
幼少の頃に川の対岸に観た“黒くて巨大な機関車”、公民館の池に泳いでいた“マグロのような大きさの鯉”、そしてある日を境に消えてしまった友人A―「意味付けなどいっさい拒否するただそれが起こったままにしか語れない不思議な出来事」を経験した私はやがて、ナイジェリアに赴任することになるのだが…。小説に内在する無限の可能性を示した傑作。
著者等紹介
磯崎憲一郎[イソザキケンイチロウ]
1965年、千葉県生まれ。2007年『肝心の子供』で第44回文藝賞を受賞しデビュー。08年『眼と太陽』が芥川賞候補に。09年『終の住処』で第141回芥川賞、11年『赤の他人の瓜二つ』で第21回ドゥマゴ文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハチアカデミー
11
B 連想と連想を紡ぎ、歪な時空間の中に独特の世界を構築する良作。磯崎氏の作家としての個性を掴むことができる、彼にしか書けない作品である。幼き頃の朧気な記憶やイメージと、時間の感覚がスピードアップする大人の記憶や行動が、母の眼という緩やかな紐によって結ばれる。すべては母が仕組んだこと、すでにかかれた日記なのではないか、すべては母に報告するための生涯なのではないか。現代の根拠なき生の不安や喪失感が、鮮やかなイメージによって描かれている。そのくせ、文章は平易で読みやすく、読者を選ばない。バランス感覚が良い。2012/06/06
はじめ
7
・世紀の発見/幻想的な雰囲気は勉強になるけれども、流れる空気が前向きでないところがあまり好きな話ではなかった。 ・絵画/ウルフの灯台へ を現代日本に焼き直した感じ。冒頭が最高。2017/12/06
たびねこ
6
磯崎作品を読むのは2冊目。話の進み方、テンポが独特だ。少年時代の思い出も、大人になってからの海外出張も、どの場面も、夢の中で起きていることのように、唐突に連なっていく。夢を見ている本人が、夢の行く先を知らないのに似て、筆者の書いた先に、予期しない物語が現れる、ということなのか。それが「発見」なのか。このクセ球、嫌いではない。2021/06/07
あんこう
6
いや、凄いわ。これが『文学』か。授業を聴くよりもこの一冊を読むことで、磯﨑先生の言う「小説とは何か」という自説が伝わってくる。何だこれは。いや、凄いわ。2019/11/27
sputnik|jiu
6
『肝心の子供』を読んだのが5年前。滋味深い文章を書く作家、という印象があったのだが、ちょっと記憶を美化しすぎたか。なんだか語りが説明くさくて、たどたどしくて、自分の中にある作家像との乖離を感じた。好きな作家ではあるんだが、なんだかなあ。『肝心・・・』を読み直すか。2017/01/07