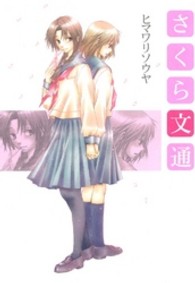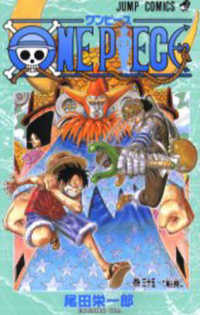内容説明
昭和初期、東京に「説教強盗」が現れた。その名は妻木松吉。その兇悪な手口から、警察は犯人サンカ説を流した。捜査当局に対抗し犯人を追う、後のサンカ小説家、新聞記者三角寛。大戦を前にして物情騒然たる帝都の、富裕な新興住宅地西北地区にねらいを定めた一世説教強盗の、謎に包まれた出自と捕まるまでの犯行経路を追う。
目次
第1章 説教強盗とは
第2章 説教強盗事件の地理
第3章 翻弄された捜査陣
第4章 説教強盗捕縛さる
第5章 新聞記者三角寛の挑戦
第6章 説教強盗「山窩」説
第7章 「山窩」の虚像と実像
第8章 「サンカ」とは何か
第9章 サンカの漂泊性と被差別性
第10章 三角サンカ学の意味
補章 サンカ再論
著者等紹介
礫川全次[コイシカワゼンジ]
1949年生まれ、在野史家。フィールドは、近現代史、犯罪・特殊民俗学。歴史民俗学研究会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gtn
12
初版において、昭和初期の説教強盗を導入部として、三角寛説を下敷きとしたサンカ論を展開する。サンカは忍者の末裔であるとの珍説を披露するとともに、三角が捏造したサンカ文字や隠語まで紹介する始末。よく言えばロマンチストである。しかし、後年、三角の学説がすべてフィクションであったことを知り、生き恥をかく。だが「サンカ研究にとっては、この一件はむしろ好機」と全くめげない。サンカと深く関わる「箕」についても再考したいと、補遺で抱負を語る著者。遅きに失するが。2019/12/15
Punk!Punk!Punk!
1
民俗学者柳田國男をも魅了した、漂泊民サンカ。本書はサンカを研究した三角寛とサンカを題材としている。三角がサンカを知ったのは、新聞記者時代追い掛けていた「説教強盗」からである。刑事が漏らした犯人は山窩という言葉からサンカに興味を持つようになる。事件は解決するが、三角は記者を辞め、サンカ研究に進む。サンカとは川漁、箕作り等を業とする漂泊民を指す。独自の文化を持ち、組織掛かった集団と考えられていたが、実際は土着の被差別民や犯罪者をサンカと括り、定着しない輩や差別的な扱いに使用したのが語源でありサンカはいない。2015/04/19
う;へ;あ;は
1
警察の体質が見えて面白い。三角寛のストーリーとしても興味深い。2014/12/23
Tomochum
1
「サンカという集団は居なかった」という立場から読了。三角寛が当時どんな立場から「サンカ」に目を向け始めたか、という面ですごく興味深い。「説教強盗」は学生の頃マイクロフィルムで己が目的もなくひたすら古新聞を読んでた時に何度も出ていたがスルーしていたキーワードだった。「ああ、今も昔もマスコミは同じ動きをする」っていうワードたちを今の世に抽出してくれた感じ。どちらも知らない知人に貸した時の反応が予想外のところから来て面白かったよ。2014/06/11
Gen Kato
1
説教強盗とサンカとの関わりに触れた一冊。この二つをつなぐワードは「警察」であったということで(そして三角寛)。2014/04/07