内容説明
芥川龍之介も、大正期の代表的名随筆集『退屈読本』を書いた佐藤春夫の人気には、当時かなわなかった。その精神は本書の名訳にもよく表われている。一方、合理的で論理的でありながら、皮肉やユーモアに満ちあふれていて、誰もが楽しめるこの『徒然草』は、きわめて現代的な生活感覚と美的感覚を喚起させてくれ、精神的な糧とヒントを与えてくれるまさに名著。
著者等紹介
吉田兼好[ヨシダケンコウ]
弘安6年頃―観応3年頃(1283年頃―1352年頃)。鎌倉後期から南北朝時代の歌人、随筆作者。二条為世門下で和歌を学び、四天王と称せられ、『続千載和歌集』などに入集される。『徒然草』は1330年頃の傑作随筆
佐藤春夫[サトウハルオ]
1892―1964年。詩人、小説家、評論家。和歌山県生まれ。森鴎外、永井荷風に師事し慶大予科文学部に入学して堀口大学と詩友になる。小説『田園の憂鬱』『都会の憂鬱』のほか、処女詩集『殉情詩集』、中国詩人名媛の訳詩集『車塵集』、随筆『退屈読本』など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- レッドピルブルーゲイザー【フルカラー】…
-
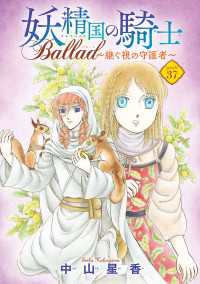
- 電子書籍
- 妖精国の騎士 Ballad ~継ぐ視の…
-

- 電子書籍
- 憧れのウエディング【分冊】 9巻 ハー…
-
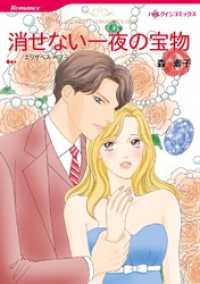
- 電子書籍
- 消せない一夜の宝物【分冊】 2巻 ハー…




