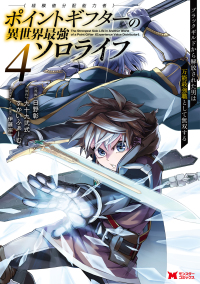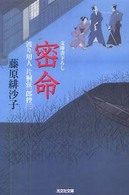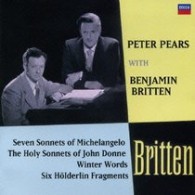出版社内容情報
オールカラーの写真と楽器の音色が聴けるQRコードが連動した画期的な図鑑。貴重な音源を豊富に収録。各楽器にわかりやすい解説付。
民音音楽博物館[ミンオンハクブツカン]
監修
内容説明
「民族楽器」とは、世界各地の、さまざまな民族によって演奏される楽器のこと。それぞれの民族が長い間育ててきた、固有の文化と密接な関わりがあります。楽器の仕組みや演奏方法にふれ、実際に音色を聴いて、その楽器がたどってきた歴史に思いをはせながら音楽の楽しさを感じてください。
目次
第1章 弦鳴楽器のなかま(三弦;琵琶 ほか)
第2章 気鳴楽器のなかま(尺八;笛子 ほか)
第3章 膜鳴楽器のなかま(小鼓;和太鼓 ほか)
第4章 体鳴楽器のなかま(アンクルン;ラナート・エーク ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
56
日本の胡弓が古代ペルシャの奏法を伝えているとか、古代オリエントの竪琴の子孫がエチオピアに残っているとか。京都には民族楽器の専門店があって、ウィンドーで見かけたことのある楽器もちらほら。西洋音楽から見たら、とても奇妙な形でも、実はどこかでつながる系統立てられたりする。背景には数百年ではすまない長い歴史があるのでしょう。残念ながら音楽は消えるものなので、実物の音、それも本物の演奏を聴いてみたいものです。2020/01/08
midorino
10
世界の民族楽器を分類ごとに紹介。QRコードがついているものは、実際の音色も聴くことができる。今まで物語に出てくる楽器をあいまいなイメージで読んでいたが、この本のおかげで具体的な形や音が思い浮かべられるようになった。楽器の分類方法(ザックス=ホルンボステル分類)があるというのも初めて知った初心者だが、分かりやすく解説されていて楽しめた。通勤中に読んでいてイヤホンを持ち歩かないので、家に着くまで音色はお預けということも多かった。文章や音色だけではなく演奏している様子も見てみたくなり、Youtubeも活用した。2019/02/20
Rieko Ito
5
多くの民族楽器が全ページカラーで紹介されている。ザックス=ホルンボステル分類に基づいてきちんと分けられているのが良い。ほとんどの楽器の音がスマホで簡単に聞けるのが長所。2018年の本なので、目の付け所は早かったと思う。解説は音の出方に特化しているが、それでよい。創価学会の民音音楽博物館の監修だが、本書に宗教性・政治性は無い。よい入門書。2023/01/03
あさみ
5
世界の楽器を分類し、紹介した本。楽器の音色が聴けるQRコード付というのが、今どきですね。ところで、昔、吹奏楽をやっていた頃、ゴン太マシーンと呼んでいた楽器があった記憶があるのですが。正式名称何だったかしら。ちょっとわからず。2019/07/07
海星梨
4
QRコードで聴けるとはすごい!と借りました。すごいですが、どうやって使っているのかわからないので結局YouTubeで調べることになります。ので、日本語だけではなく英語と使われてる国の言語でも楽器の名前が欲しかったです。 あとは、楽器の分類のしかた、ザックス=ホルンブステル分類とかいうのもこの本で知りました。調べると楽器分類学なるものがあるそうです。興味津々です。 他の本やらなんやら紹介があったらなーとも思いました。民音音楽博物館、実際に楽器をさわれるそうで、めっちゃ行きたいです。2018/11/05
-
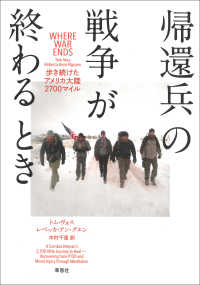
- 電子書籍
- 帰還兵の戦争が終わるとき: 歩き続けた…