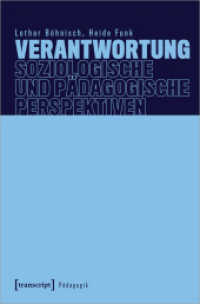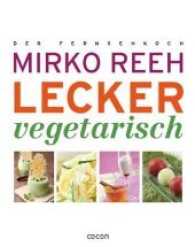出版社内容情報
柳田国男の全集未収録文集。日本人の生きてきた精神風土にふれる、柳田ならではの読み応えに充ちている。
【著者紹介】
1875年兵庫県生まれ。農商務省勤務、貴族院書記官長を経て、1930年代以降は民俗学の著作に専念し、研究会や雑誌を主宰した。おもな著書に、『遠野物語』『木綿以前の事』『海上の道』など。1962年没。
内容説明
「日本の文化は日本人でなければ研究出来ないと思う。」新生日本のために、まず日本人の特性を見つめ掘り下げた、柳田学の核心部を一冊にまとめる。戦後70年記念出版。
目次
考えない文化
日本の笑い
処女会の話
離婚をせずともすむように
うだつが上らぬということ―家の話
日本人とは
家の観念
日本における内と外の観念
私の仕事
無知の相続
日本人の来世観について
私の歩んだ道
柳翁新春清談
次の代の人々と共に
著者等紹介
柳田国男[ヤナギタクニオ]
1875年、兵庫県生まれ。民俗学者。1962年没。旧姓・松岡。短歌、新体詩、抒情詩を発表。東京帝国大学を卒業後、農商務省に勤務。貴族院書記官長を経て退官、朝日新聞社に入社。1909年、日本最初の民俗誌『後狩詞記』を発表。翌10年、『遠野物語』刊(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
32
日本人の言う事は本当かも知れぬといった様な信用を持たせる問題。今日は誰もやらない(12頁)。今では安倍がうそつきばかりで、円という通貨価値が落ちないことを願う。うだつ(卯建)は奈良朝時代まで逆のぼることが出来る。正倉院建築の文章に出ているとのこと(59頁)。元来日本人は、思った以上に、ものごとを強く変えてゆくことを喜ぶ性質をもっていたのではあるまいか(64頁)。大黒柱は2本。小黒柱もある(68頁)。民俗学の根本基礎:知識をもてば判断する。知識供給を豊かにし、未知も認める。2015/11/15
れどれ
6
物事の考え方のチャンネルを一つ増やしてくれる、そういう作用のある発展的な切り口。もんくなく面白かった。大勢について述べた一連の文章は誰も彼もに読み聞かせてあげたい。2018/12/16
にゃあ
5
高田崇史さんの本で頻出(している気がする)柳田國男さんのエッセイ集。世界と比較する前に日本の文化を知るのが先で、日本のことは日本人自らが研究すべきという思いで民俗学ができたと知る。印象に残った文はつぶやきとして残した。「民俗学」などと称すると敷居が高くなるので、なにかもう少し気楽に臨める呼称があればな、と思った。(かといって「むかし話」も違和感…)ゆくゆくは口語版の遠野物語を読んでみたい。2020/09/27
徳島の迷人
4
表題が凄いが、柳田国男の晩年の約10年の発表をまとめたもので、エッセイに近い。民俗学の記述は多いが、自己啓発的な記述やこれからの日本人や学者の生き方への提言も多い。男女論や結婚論、うだつのこと、墓についてなど。「未婚の同性たちで集団を作るのが良いのでは」という説は印象に残った。終盤に自伝が載っているが、官僚の生活や小説との出会いの話は面白い。柳田国男が民俗学の基本なのかしら、全く知らない衝撃的な記述は無かったと思う。研究を深めていくべきだとする提言の、次の研究結果を読んでみたい。2021/10/15
mitsuru1
4
いろんな所に発表した14のエッセイ集でした。明治から昭和戦後まで生き抜いたまさに民族学の巨人の面目躍如か。思う存分旅が出来た理由には笑った。いろいろ有ってもやはり旧き良き時代か。2015/08/17