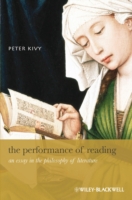内容説明
企業の不正や事故のリスク、過重労働、児童虐待もみんな見て見ぬふり。波風を立てたくない、心配をかけたくない、苦しい決断をしたくない、自分の信念を捨てたくないといった心理から起こる傍観者の態度を詳しく分析。
目次
似た者同士の危険
愛はすべてを隠す
頑固な信念
過労と脳の限界
現実を直視しない
無批判な服従のメカニズム
カルト化と裸の王様
傍観者効果
現場との距離
倫理観の崩壊
告発者
見て見ぬふりに陥らないために
著者等紹介
ヘファーナン,マーガレット[ヘファーナン,マーガレット][Heffernan,Margaret]
受賞経験もある企業の社長であり、著述家であり脚本家。アメリカ・テキサス州生まれ。ケンブリッジ大学卒。BBCラジオで5年間ドキュメンタリーやドラマの制作に携わったのち、テレビのドキュメンタリー番組のプロデューサーも務めた。ソフトウェア業界やインターネット業界での経験もある
仁木めぐみ[ニキメグミ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
funuu
7
アメリカのサブプライム問題、イラクのアブグルイブ刑務所での米兵の捕虜虐待事件、神父による児童への性的虐待に対するカトリック教会の対応、BP社の製油所爆発事故、スペースシャトル チャレンジャー号の打ち上げ失敗 ここに挙げた事件、事故などの背景にはすべて「見て見ぬふり」がありました。勤続36年目、「見て見ぬふり」をして、生きましたね。2015/01/25
1.3manen
7
傍観者効果とは、心理学者のダーリーとジェネヴィーズが発見した。危機的状況を目撃した者が多いほど、行動する人が少ない(219-20ページ)。誰かが通報してくれる筈だという思い込みがその場の人間たちを支配しているのだ。奇妙な無責任にして安心してしまっている。矛盾。日本の場合はいじめ問題の温床。快楽のトレッドミルとは、快楽中毒症(269ページ)。臭いものには蓋を、或いは、排除の論理。こうしたものは、集団や組織においてその存続基盤を破壊する。社会の意味を問わざるを得ない。気候変動や国益という外交も共生を志向する?2013/01/09
midnightbluesky
5
人が多ければ多いほど声をあげることに勇気がいる心理について詳しく解説。なるほどと思うこと多し。2012/09/30
MasakiZACKY
5
気づいていたはずのことに気づかず、現実を直視せず、見て見ぬふりをしてしまうことについて述べた一冊。何故それが起こり、その先に何が待っていて、我々はどうすればよいのか。様々な事例や研究をもとに書いてある。「見て見ぬふり」とは意識的に聞こえるが、実際は無意識に起こり、後から気付く愚かさ。後になっても気づけない恐ろしさ。それがほとんど本能である以上、まずはその実態を認識することから始めるしかない。そのためにも本著は最適である。特に日本社会は性質上かなり危ないと感じた。カサンドラを周りに呼び、自身もカサンドラに。2012/06/28
くさてる
5
人間はいかに見えるものを無視し、見たいものしか見ないのか。読んでいてずっと苦しかった。自分自身の視野の狭さを指摘されていると感じたからだ。そしてなおかつ、この問題のさなかにあるたくさんの人々の存在も想像できたからだ。様々な例が挙げられるなか、もっとも衝撃を受けたのは、妊婦へのレントゲン照射がどのような影響をもたらすかを警告したアリス・スチュワートの例だった。ほかにも多くの悲劇がごく普通の人々の常識的な対応によってもたらされたことがひどく哀しい。繰り返したくないと感じた。、2012/01/21
-

- 和書
- 公企業会計の研究