内容説明
ドゥルーズに影響を与え、いままたラッツァラートら新鋭の思想家によって復活されつつある忘れられた社会学者タルドの主著、初の日本語全訳。発明と模倣/差異と反復の社会学を展開する歴史的名著。
目次
第1章 普遍的反復
第2章 社会的類似と模倣
第3章 社会とは何か?
第4章 考古学と統計学―歴史とは何か?
第5章 模倣の論理的法則
第6章 超論理的影響
第7章 超論理的影響(続)
第8章 考察と結論
著者等紹介
池田祥英[イケダヨシフサ]
1973年生まれ。ボルドー第2大学でDEA(社会学)取得。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。現在早稲田大学文学学術院・武蔵大学社会学部非常勤講師
村澤真保呂[ムラサワマホロ]
1968年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位取得退学。現在龍谷大学社会学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし
8
暇がなくて急いで読み流しただけだが、柳田国男の文化発展論に近い。周圏論などはほぼタルドの模倣論の日本の方言への応用。柳田がこれを読んだかどうかは不明だが、ドイツ的な伝播論と英国風の進化論の相剋という自分の柳田解釈はどうやら的を外してた。タルドにおいてもすべての文化の源は天才による発見・発明であるが、それが進歩に結びつくのは模倣のメカニズムによる。ただ、非人格的な模倣の法則においてはやはり主体性が消失する。柳田が後に自分の周圏論に距離を置きはじめるのも、やはりドイツ的な主体性の問題からではなかったかと思う。2024/08/27
ゆうき
5
社会が個人へと影響を与える方法論的全体主義では、なく個人が社会に影響を与えるという方法論的個人主義を「模倣」というキーワードで社会を分析した一冊。まず最初の発見があり→個人間で模倣が行われる→社会が形成されるという一連の流れにおいて社会は個人による「模倣」の連続によって形成され。伝統も「模倣」されることで伝統となり、そこに新たな発見が加わることでまた模倣をされる。この社会は「模倣」というコピーの連続でなりたっており、その社会を形成するのは模倣をする個人である。2013/05/08
イボンヌ
4
難解な本で、斜め読みした。 全ては模倣から始まる事は、間違いなさそうです。2025/11/05
ppp
3
物理学、生物学、(人間)社会学において、反復(としての振動)を基礎概念とし、そこから種々の現象を説明しようとする。波動との類比から強め合いや干渉が生じること、外的模倣と内的模倣の関係、習慣・慣習的なものと流行的なものの差異など、一口に模倣といっても、様々な法則的側面がある。19世紀末期にもかかわらず(だから?)、ビックリするほど現代的な考えが展開されるが、説明モデルと実証が合致しているかについては疑問に感じた。また、模倣の果てにタルドが描く世界像は、驚くほど一様かつ楽観的なもので、これには違和感があった。2012/10/29
あとがき
2
「社会とは模倣である」/模倣が社会現象の根源的要素という指摘は、かなり正しく先見的だ。閾下知覚レベルでの模倣の発見などよりも、かなり早い時期に模倣の重大性を看破している。オリジナリティや個性が重視され、模倣というとネガティブに響く時代だからこそ、示唆に富む議論だ。/ただし、模倣だけで社会的なものの一切が、心理学に還元して説明可能というのは言い過ぎだろうし、デュルケムの批判もそこにあろう。「卓越化」や「役割距離」など、その後社会学が発見した「反-模倣」的概念の説明をタルドの模倣一元論は果たせないように思う。2024/02/09
-

- 電子書籍
- 【単話版】穏やか貴族の休暇のすすめ。@…
-
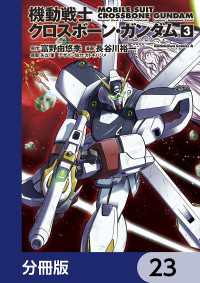
- 電子書籍
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム【分冊版…
-
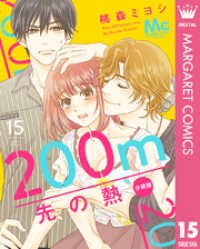
- 電子書籍
- 200m先の熱 分冊版 15 マーガレ…
-

- 電子書籍
- 間違いで求婚された女は一年後離縁される…
-
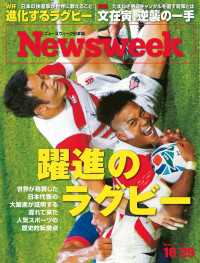
- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版 2019年 1…




