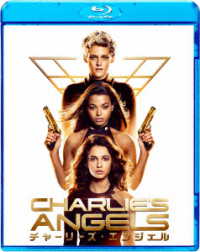出版社内容情報
南太平洋に浮かぶ島に訪れた私は、島の歴史に隠されたある「過ち」を知る――自然/文化の境界が揺らぐ先に浮上する「新たなる自然」とは何か? 気鋭による文化人類学の新地平。
著者情報
1980年生まれ。早稲田大学人間科学学術院准教授。文化人類学、メラネシア民族誌。著書『「海に住まうこと」の民族誌』、共訳書ストラザーン『部分的つながり』、デ・カストロ『インディオの気まぐれな魂』など。
内容説明
フィールドワークに基づく近代人類学の誕生から100年、「ポストコロニアリズム」「存在論的転回」「マルチスピーシーズ民族誌」などを経て、人類学はどこへ向かうのか?南太平洋でのフィールドワークと哲学/思想や文学を峻烈に交差させ、人類学を「外部としての自然」へと解き放つ新たなる思考。人類学的思考の根源を現代に回復し、世界の見方を根底から変える衝撃作!
目次
はじめに―「ツナミ」の後で
第1部 他者(人類学/民族誌の現在;浮上する「自然」)
第2部 歴史(歴史に抗する島々;イメージとしての島々)
第3部 自然(生きている岩;沈む島々)
著者等紹介
里見龍樹[サトミリュウジュ]
1980年東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程単位取得退学。博士(学術)。早稲田大学人間科学学術院准教授。専門は文化人類学、メラネシア民族誌。著書に『「海に住まうこと」の民族誌―ソロモン諸島マライタ島北部における社会的動態と自然環境』(風響社、2017年。第四五回澁澤賞、第一七回日本オセアニア学会賞を受賞。また同書のもととなる博士論文に対し第一五回アジア太平洋研究賞を受賞)、『二十一世紀の文化人類学 世界の新しい捉え方』(新曜社、2018年、共著)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
塩崎ツトム
mikio
瀬希瑞 世季子
文狸
Kaname Funakoshi
-
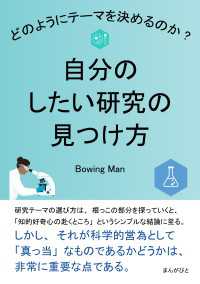
- 電子書籍
- 自分のしたい研究の見つけ方 どのように…
-

- 電子書籍
- 週刊パーゴルフ 2020/10/27号