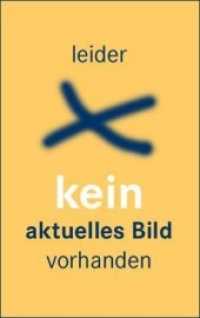内容説明
いきつくところは「笑い」。親鸞が浄土の教えを津々浦々に広めようと始めた念仏、和讃、そして説教…その現在に立ち会い、新しい法要造りに参加した著者が、現代の心の置き所を親鸞に見出す魂の旅。
目次
はじめのはじめの、つれづれに…
1 元祖浪花節・親鸞聖人?
2 仮に来て、教えて帰る…
3 光顔巍巍・威神無極
4 信心があろがなかろが…
5 猿楽法師・蓮如上人
6 宮商和して自然なり…
7 天竺問答・親鸞聖人和讃事始
8 念仏往生・清浄楽正信偈次第
はじめのおわりの、うたかたは…
著者等紹介
伊東乾[イトウケン]
1965年生まれ。作曲家=指揮者。ベルリン・ラオム・ムジーク・コレギウム芸術監督。東京大学大学院情報学環・作曲=指揮・情報詩学研究室准教授。東京大学理学部物理学科、同修士課程、同総合文化研究科博士課程修了。第一回出光音楽賞ほか受賞。創作・演奏の傍ら脳認知生理学に基づく音楽表現の国際基礎研究プロジェクトも推進する。『さよなら、サイレント・ネイビー』(集英社文庫)で第四回開高健ノンフィクション賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
22
メモ。「古代から本当に『お経』と思われてきたのは『詩』なんですね」(45)。「釈迦入滅後、釈尊の弟子つまり比丘たちが集まって、おのおの記憶しているものを「ともに歌って」記憶が定かであるか確かめあうことになった。そこで異同があれば合議して調整した、それが元来の『仏典結集』の姿」(44)。「生前『文字の使用』を厳禁した釈迦の教えに従って、原始教団の仏教はもっぱら記憶と暗誦によって伝承されていた。『ともに歌う』結集が開かれ、いつしかそれが文字として記録され、編集されていった」(44) 文章内の言葉適宜省略有り2019/08/25
小鈴
20
真宗大谷派の雑誌から執筆依頼を受けた著者は、真宗といえば「節談説教」ていうものがありますよね、とはじまり、真宗の門外漢であっても著者の関心の赴くまま真宗、仏教、宗教と歌という深く広い世界につれていってくれる。著者は名古屋の大谷派の寺院のお坊さんともに作った「清浄楽雅楽法会」を東別院で行うのだが、読んでいて映像が浮かび正信偈が鳴り響く。本を閉じて余韻にひたる。とても心地のよい気分に浸れた読書であった。2019/08/24
kenitirokikuti
8
表題の「笑う親鸞」を巡る話は序盤のみで、おおむね真宗大谷派の礼拝のオトの側面が論じられる▲名古屋の浄信寺は代々東本願寺楽頭を務めていた。浄信寺九世羽塚慈明(号・秋楽院)が還暦のころ御一新があり、彼は「宮内庁楽部」設立に尽力した。近代雅楽界は彼の門人からなるといっても過言ではない▲「ウケる」とは「受け念仏」から来ている。説教を聞く門徒が有難いと感じたときに「ナムアミダブツ」と呟く▲畳に漆喰の白壁が和様の部屋だが、僧や仏像のエリアは唐様、具体的は漆塗りの板張りで、ピアノやバイオリンの木製ボディと同じ。2019/09/21
新井徹
3
親鸞は様々な読み方が出来てすごい。「親鸞という人は、自身もよく笑ったに違いない。また座を共にする人々をよく笑わせた人に違いない。残念ながら、何故そう思ったか、理由を問われても上手く答えられない」。根拠レスにそう思わせてしまう魅力。読者は、このひらめきの検証に付き合う訳だけど、よく出来た読み物は、よく出来た推理小説に似ている。この著者は、あの「さよなら、サイレント・ネイビー」を書いたひとなんだけど、親鸞って、そのひと自体のすごさもさることながら、親鸞に魅了された人たちがまたすごく魅力的ってところがあるよね。2012/09/02
中年親爺改め老年親爺
2
浄土真宗にまつわる音楽の世界。寺のお堂とヴァイオリンやピアノが、音響効果の構造が同じだった。その心は「魂柱(こんちゅう)」だという。お経の核心部分は歌(詩)に編集され、庶民に伝えられた。そこから派生して、能楽、雅楽などが生まれ、現代の演歌に繋がると言う。七五調の共通点から、親鸞が編んだ和讃(お経)が北の宿からのメロディに載ってしまう件には、笑えた。難解なことを、無関心な人にも説く、方法論のヒントを見たような気がする。2013/06/13
-
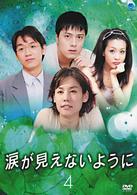
- DVD
- 涙が見えないように Vol.4