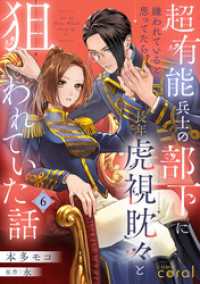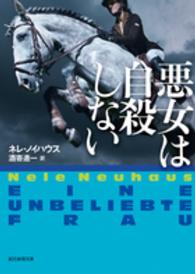出版社内容情報
差別され賤視された漂泊放浪民は、どこに隠れ住んだのか。『日本の「アジール」を訪ねて』(2016)に、山形市・極楽寺に住んだ院内・イタカ、下妻市の筬屋・箕直しの章を増補し、改題。
著者情報
1944年生まれ。民俗研究家。 著書に『サンカの真実 三角寛の虚構』『葬儀の民俗学』『新・忘れられた日本人』『サンカの起源』『猿まわし 被差別の民俗学』など。
内容説明
戦後まだ、各地で、乞食、サンカ、病者、芸能民、被差別民などの漂泊放浪民が移動生活を行なっていた。彼らが社会制度をはずれ、棲息した、洞窟などの拠点「アジール」を訪ね、その暮らしの実態を追うノンフィクション。旧著『日本の「アジール」を訪ねて』に新たに「院内」の章を加える。ある戦後史の貴重な記録。
目次
第1章 サンカとハンセン病者がいた谷間
第2章 土窟から上る煙
第3章 大都市わきの乞食村
第4章 カッタイ道は実在したか
第5章 洞窟を住みかとして
第6章 有籍の民、無籍の民
第7章 川に生きる
第8章 地名に残る非定住民の歴史
第9章 「院内」:寺院の境内にもアジールがあった
著者等紹介
筒井功[ツツイイサオ]
1944年、高知市生まれ。民俗研究者。元・共同通信社記者。正史に登場しない非定住民の生態や民俗の調査・取材を続けている。第20回旅の文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ROOM 237
13
無戸籍で非定住という少数の人々が日本でどう暮らしていたのか?著者は当事者である内側の視点を重視し、刑事ばりの聞き込みフィールドワーク魂で慎重に事実を紐解き他の学者の虚構を暴く。豊富な写真を眺めイメージし読み進めると、民俗語彙とその語源となる生業や寝食場所は関東〜九州で相違があるのがわかった。山腹の横穴墓古墳で煮炊きする集団暮らし、家族の場合は役割分担など克明に記されている。気がつくと土窟から姿を消しているという彼らに加え、乞食やハンセン病者にも触れており、非定住者の人目を避ける心理が少しだけ理解できた。2023/08/30
hirokoshi
1
本の趣旨とは外れるけど、ハンセン病は現在では「感染力が弱く、大人は免疫力があるので発病につながらない(ただし乳幼児は免疫力をまだ獲得していないので注意)」と判明しているらしいので、ただ伝染病とだけ記すのは偏見の助長になってしまいかねないのではと気になる。天王寺の清水精一の「自分自身の生き方と家族の意思の尊重は別」という腹の決め方尊敬する。P118 さらっと差別からくる冤罪に触れてる。何度も否定的に引用されてる三角寛、それはそれでちょっと読んでみたくなる。(私にとってはどちらが“正しい”かはわからないし)2025/01/11
amaken
0
市民図書館 三角寛のサンカ奇談を読んで、図書館で借りた。 こちらはノンフィクションなんですね。2024/08/11