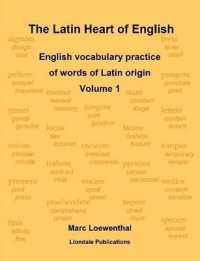- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
近年、同調圧力、自粛警察という言葉の登場とともに、「村八分」が脚光を浴びている。そして今なお村八分に苦しむ人がいる。日本の精神風土に顕著な制裁行為の歴史をたどる初めての研究書。
著者情報
1949年、東京生まれ。ノンフィクションライター、在野史家。主な著書に、『史疑 幻の家康論』『異端の民俗学』『知られざる福沢諭吉』『サンカと三角寛』『日本人は本当に無宗教なのか』『独学文章術』など。
内容説明
21世紀の現在も、なお耳にするこの言葉。ムラ的な社会がある限り、村八分はなくならないのか―。日本特有の「同調圧力」とも言える村八分の歴史をたどり、村八分論を初めて一冊にまとめた歴史民俗ドキュメンタリー。
目次
第1章 「村八分」とは何か
第2章 なぜいま「村八分」なのか
第3章 村八分の歴史(江戸期)
第4章 村八分の歴史(明治大正期)
第5章 村八分の歴史(昭和期)
第6章 村八分の研究史
第7章 村八分を描いた作品から
第8章 村八分研究の課題
著者等紹介
礫川全次[コイシカワゼンジ]
1949年、東京都生まれ。ノンフィクションライター、在野史家。主なフィールドは、近現代史、犯罪・特殊民俗学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
JILLmama
18
もう少し掘り下げてほしかったなぁ。村八分の歴史や事例を羅列しているだけであまり得るものはなかったな。2022/12/04
さわ
8
図書館の新入荷コーナーにあった本。「村八分は集団による制裁である。この制裁の心意は学校教育に今なお生きていて〜」p122に納得。【図書館本】2023/02/17
inokori
7
これはもう一度読む。 通俗道徳とは何か、という問いにもつながる。2024/07/13
てくてく
6
過去の遺物と思いがちだが、近年にも訴訟となることがある「村八分」について、関連する資料をもとに考察した本。出てくる事件や研究者・資料に見覚えがあるものがあって楽しく読んだ。近世における建前と私的制裁の関係、「共同体崩壊の過程で村八分が発生する」に関する指摘など、なるほどなと思う箇所があった。2024/12/11
なー
5
私の思っていた村八分とは、『共同体が秩序を保つため、はみ出た者達と8分の交際を断つこと。ただし2分(火事と葬式)だけはその限りではない』…という物だったけれど、それだけではなかった。盗み等で村に迷惑をかけたとかだけでなく、村が間違ってる時に正しい事を言った人まで村八分にされたりしている。理由は「村の恥を告発したから」ですって。えー…って感じ。沢山の事例を基に分かり易く説明してくれる良い本だった。村八分、今も普通にあるんだろうなあ。田舎移住に失敗した話とか結構聞くもんなあ…。2025/06/17
-
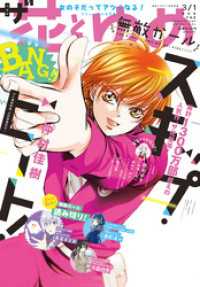
- 電子書籍
- 【電子版】ザ花とゆめ無敵ガール(201…