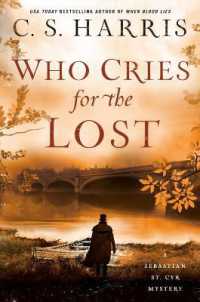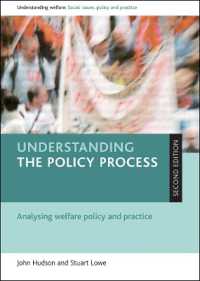出版社内容情報
「決闘」、いかに生まれ、なぜ衰退したのか。ルール、社会的背景、使われた武器など、あらゆる角度から決闘の奥深い歴史を追う。
内容説明
男も、女も、ゲーテもニーチェもマルクスも、なぜあれほど熱狂したのか。命がけの一騎打ちはいかにしてスポーツに変わったのか?ヨーロッパ精神の根底に流れる「決闘」の歴史を辿る、はじめての書。
目次
プロローグ ドイツにおける決闘体験記
第1章 決闘のヨーロッパ史
第2章 ヨーロッパの決闘禁止令
第3章 ドイツの学生と将校の決闘
第4章 決闘からスポーツへ
第5章 劇場型スポーツと観客
エピローグ 決闘の美学・スポーツの美学
著者等紹介
浜本隆志[ハマモトタカシ]
1944年、香川県生まれ。関西大学文学部教授を経て、名誉教授。ヴァイマル古典文学研究所、ジーゲン大学留学。専攻はヨーロッパ文化論、比較文化論。著作多数
菅野瑞治也[スガノミチナリ]
富山県生まれ。京都外国語大学教授。文学博士。ドイツのマンハイム大学留学中に学生結社「コーア・レノ・ニカーリア」の正会員となり、決闘を体験。現在は同会OB会員。専攻は決闘文化論、ドイツ語圏の社会文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
86
80年にドイツの学生団体に属し、学生同士の決闘(メンズーア)に参加した、珍しい経験を持つ著者と、文化史家による共著。決闘が古代の神明裁判に由来し、近代に入るまで(ドイツ・オーストリアでは現代でも)行われている事実や根深さに怖気が走らなくもなし。後半の濱本氏の、反知性主義と知性主義の分類が、本人の「良いと思っているモノ」の列挙が知性主義であり、それに反するものは「反知性主義」とレッテルを貼っている所に、本邦インテリが如何に自己を客観視できぬと言う愚かさを見せつけられた。菅野氏の単著で良かったのでは?と思う。2022/04/04
サケ太
26
面白い一冊。著者の一人菅野瑞治也氏のドイツでの決闘(メンズーア)した体験から始まり、歴史的な決闘というものの存在、立ち位置について語られる。神明裁判の一形態である決闘は、時に誇りを護るため、防衛のための手段となっていた。ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ。様々な地域で行われた決闘は、法的な規制の及ぶ事となる、そこからスポーツへとつながるところが面白い。決闘は、神明裁判の一形態から、人々の熱狂渦巻くエンタメと化すことでその意義を失っていく。スポーツとのポピュリズム、反知性主義との関連も指摘しており興味深い2021/10/24
Jampoo
8
神代の昔から近代まで決闘の形式や社会的位置付けについて書かれている。名誉と武勇を重んじる騎士階級や軍人が好んで行い、為政者はそれを禁じようとするもなかなか完全に潰す事ができなかったヨーロッパの決闘は、日本の中世でいう後妻打ちや喧嘩両成敗とかにも少し似ている。 決闘の具体的な決着基準の変遷や個別事例などもっと細かく知りたい部分はあるが最初に読む決闘の本としては良かったかなと思う。 後半部分では決闘から祭事やスポーツについて語られ、スポーツの役割と反知性主義の話などは予想外に面白かった。2025/04/22
depo
3
図書館本。図書館の新刊のコーナーにあったので、面白そうに思い借りてきた。ヨーロッパにおいて、いかに決闘が一般的に行われていたか。ゲーテやビスマルクまで決闘を行い、夜警国家と語で有名なラッサールや、ロシアの国民的詩人であるプーシキンが決闘で死んだとは、初めて知った。2021/11/15
bibi
2
実際に決闘を行った著者の証言もあり、前半の内容は非常に参考になった。由来はともかく、中世以降は個人的な戦争であり、名誉や勇気などという高尚な動機は特権階級による後付けの理由に過ぎないだろう。理性と合理を重んじる為政者ならば決闘禁止令を出すのは尤もだと思われる。ところで後半はスポーツの話になり、決闘史の本筋からは少々ずれて、読み続けるのが辛かった。別書として出版した方が良かったのでは…? 語句の説明のために著者が作成した分類も唐突感が否めない上に、ますます誤解を招くと思われる。後半のために読後感がいまいち。2022/06/10