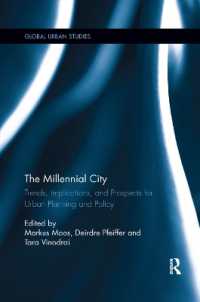出版社内容情報
近代化と共に変容を遂げてきた“武士道”の本質を、「戦陣訓」からひも解く。戦後70年、日本人の拠り所になってきた精神性とは。
【著者紹介】
1950年、山口県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。同大学院博士課程修了。現在、明治学院大学教授。専攻は日本古代史。歴史哲学。日本の思想・文化の研究に取り組む一方、広範な分野での執筆活動も行なう。
内容説明
平安末期の「弓馬の道」江戸中期の『葉隠』明治に入ってからの『武士道』…近代化と共に変容を遂げてきた武士道の本質を『戦陣訓』からひも解く。
目次
序章 いくつもの戦場で玉砕命令の根拠とされた『戦陣訓』とは何か
第1章 武士道が生まれた理由(武士道に教本はない;平安時代なかばから室町時代までの武士と武士道;戦国時代、安土桃山時代、江戸時代の武士道)
第2章 近代国家の新たな軍隊の誕生(国家を意識した幕末の武士道;明治維新と日本軍の成立;山県有朋と軍制の整備;『軍人勅諭』の下賜とその役割)
第3章 『戦陣訓』成立への流れ(対外戦争の時代の訪れ;近代化の中での武士道の変化;あい次ぐ戦争と軍部の勢力拡大)
第4章 『戦陣訓』とその影響(『戦陣訓』の本文(簡単な解説を付す)
日本の敗戦と『戦陣訓』の役割)
著者等紹介
武光誠[タケミツマコト]
1950年、山口県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。同大学院博士課程修了。文学博士。現在、明治学院大学教授。専攻は日本古代史、歴史哲学。日本の思想・文化の研究に取り組む一方、広範な分野での執筆活動も行なう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
り こ む ん
さり
-
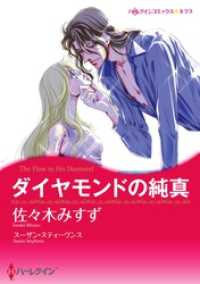
- 電子書籍
- ダイヤモンドの純真【分冊】 12巻 ハ…
-
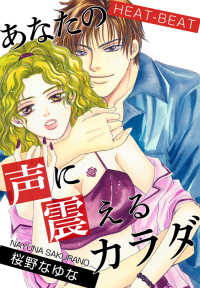
- 電子書籍
- HEAT-BEAT~あなたの声に震える…