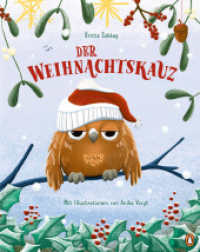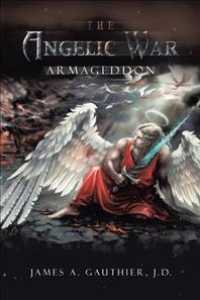出版社内容情報
厳しくも慈愛溢れる父や伯父の生き様は古き良き中国を体現していた。文革、貧困、戦争……ノーベル賞候補作家による感動のエッセイ。
閻 連科[エン レンカ]
1958年、中国河南省の貧しい農村に生まれる。20歳で解放軍に入隊。在軍中に河南大学と芸術学院を卒業。2004年に軍を離れ、作家生活に専念。『堅硬如水』で魯迅文学賞、『受活』で老舎文学賞を受賞。現代中国を代表する反体制派の作家。
飯塚 容[イイヅカ ユトリ]
1954年生まれ。中央大学文学教授。訳書に、高行健『霊山』『ある男の聖書』(集英社)、余華『活きる』(集英社)、『ほんとうの中国の話をしよう』(河出書房新社)、蘇童『河・岸』(白水社)など。
内容説明
小学校の美しい先生、都会から来た女の子、下放で村を訪れた知識青年たち、難病を患う長姉、毛沢東語録、『紅楼夢』…。父の世代の苦労と努力は、次の世代を育む土壌・陽光・雨水であった。人間の尊厳と人生に対する深い理解を示す傑作エッセイ。
著者等紹介
閻連科[イエンリエンコー]
1958年中国河南省嵩県の貧しい農村に生まれる。高校中退で就労後、20歳のときに解放軍に入隊し、創作学習班に参加する。1980年代から小説を発表。軍人の赤裸々な欲望を描いた中篇『夏日落』(92)は、発禁処分となる。その後も精力的に作品を発表し、中国で「狂想現実主義」と称される『愉楽』(2003)は、05年に老舎文学賞を受賞した。一方、長篇『人民に奉仕する』(05)は2度目の発禁処分となる。さらに「エイズ村」を扱った長篇『丁庄の夢』(06)は再版禁止処分
飯塚容[イイズカユトリ]
1954年生まれ。中央大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
燃えつきた棒
けいと
きゅー
みんみん