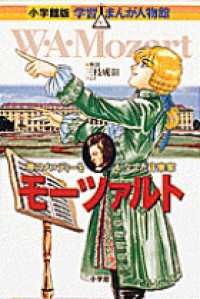出版社内容情報
根源的な場を追求した巨人・熊楠をもうひとりの巨人・大拙と対照させながら生命と霊性の核心へ挑む最も重要な批評家の力編。
内容説明
粘菌と曼陀羅の探求から生命と非生命、精神と物質の差異から森羅万象の根源へ、そして「森」のエコロジー、「森」のアナキズムへ―未曽有のスケールで世界的にして未来的な思想を探り出した巨人・熊楠。その可能性を大拙、井筒、そして世界と共振させる中から未来の哲学をたちあげる。30年をかけた熊楠探求の総決算にして新たなる転回。
目次
粘菌・曼陀羅・潜在意識
神秘と抽象
生命と霊性
「宇宙模型」としての書物
一人の両性具有者の手記
著者等紹介
安藤礼二[アンドウレイジ]
1967年、東京都生まれ。批評家。多摩美術大学美術学部教授、同芸術人類学研究所所員。「神々の闘争 折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作、『神々の闘争 折口信夫論』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、『光の曼陀羅 日本文学論』で大江健三郎賞、伊藤整文学賞、『折口信夫』で角川財団学芸賞、サントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
春風
10
批評家である著者の熊楠にまつわる論考・エッセイを収録。熊楠の周辺を論じたものが多く、主眼が熊楠でないことも多々。著者の前著との関係もあるのか、鈴木大拙という普通熊楠と対比されることの少ない人物が特にフォーカスされて取り上げられている。知の巨人として知られる南方熊楠は、その特異な才能からか本人を視点人物にしたかのような論じられ方が多い。本書では熊楠の先達に当たる人物の営為と、同時代の思想家との直接・間接(書簡等)の交流を点検していくことで、熊楠がどのようにその思想を涵養していったのかが丁寧に考察されている。2021/05/23
林克也
3
とても参考になった。特に最後の2章 稲垣足穂について書いた”「宇宙模型」としての書物”と、フーコーと熊楠との関係を記した“一人の両性具有者の手記”は、この本のここにこれを入れるか?という、安藤さんの作戦に、してやられた!まいりました。というしかありません。 読み終えて、熊楠や大拙本人の著書を読み解くのではなく、安藤さんが解析し整理した本を読むという行為は、ある意味、熊楠や鈴木大拙の生き方や思想に憧れを持つ人にとっては「ハウツー本」を読む心理に相当するものなのではないかと思った。2021/10/08
ロータス
2
熊楠だけでなく鈴木大拙やブラヴァツキー、スウェーデンボルグらの思想と仏教、神智学、神秘主義についても触れられておりとても面白かった。この本を読み、彼らが見た二元論を超えた世界のヴィジョンを共有できた気がする。ミシェル・フーコー、稲垣足穂、江戸川乱歩の章も興味深い。そのうちブラヴァツキーやスウェーデンボルグの本も読んでみたい。2022/02/05
ishii.mg
2
熊楠思想の成り立ちを大拙との関係、スウェーデンボルグや神秘思想、進化論のと関係を掘り起こす。エコロジーありアナキズムありの混沌とした時代。様々な学問の起源と未分化の時代だからこそ、熊楠のような綜合する思想が成り立ったのだと思う。大拙のように全体主義にあたえた影響などを注意深く見ながらもまずは大づかみに。2021/07/13
yokkoishotaro
2
鈴木大拙との対比は熊楠の見方をクリアにしてくれたと思う。中沢新一著の『レンマ学』と合わせて読むとまた理解が深まっていくかもしれない。逆に、大拙に挑戦してみようかとも思った。2021/06/07
-
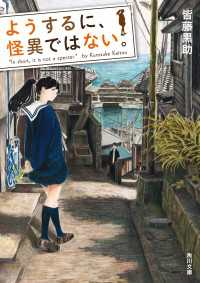
- 電子書籍
- ようするに、怪異ではない。 角川文庫