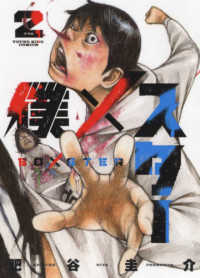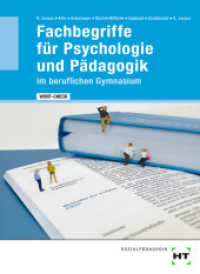目次
「絶対文芸時評」に向けて
遊戯の教訓
中断と鎮魂
批評と誘惑
文体の不幸とユーモア
複数であることの倫理
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
14
90~92年、3か月おきの文芸時評集。まとまった主張というよりも、その時々に試される反射神経の記録に思える。本のページあたりの金額価値を作家ごと(春樹、島田、古井、蓮實自身など)に測る遊戯や『男流文学論』の文学信仰への嫌味などは鋭く刺さるし、井上究一郎や後藤明生への賛辞もそれぞれ印象深いが、砂のように流れて胸に残らない感じがある。時評家の定義のように頻出する「絶対」や「ジャーナリスティック」という言葉は、このような「残らなさ」を意味しているのだろうか。まぁ全部面白いからそれでよいのだけど。2022/09/28
mstr_kk
10
再読。初読のときとはだいぶ違う印象。面白いところはいろいろあるけれど、全体に雑で、単なる韜晦に堕している部分が多いと思います。ちゃんと推敲してるのか? っていうくらい、蓮實重彦にしては文章が甘い(編集の校正も甘い)。カギカッコつきの「文学」という概念の用い方とか、ちゃんと効いていない。そもそも序文からして、何が「絶対」なのか曖昧です。『表層批評宣言』の10分の1くらいしかよくない本だと思います。ていうか、さすがにそろそろ僕も、蓮實さんに飽きたのか。2018/07/04
mstr_kk
6
蓮實さんの文章を味わうためだけに、単にエンターテインメントとして読みました。読んだ目的に完璧にかない、とても面白かったです。2014/08/17
急性人間病
5
文学をして“自分だけが知り思ったことを自分一人の文章で書く”ものとする定義へのアンチテーゼの模索を主とする時評集。『複数の書き手』=自分以外のテキストに身を浸からせる重要性というのはそれこそ(この本でも幾度か言及される)高橋源一郎が「一億三千万人のための小説教室」で指南していた“赤子のように文章を真似する”ことにも通底しそうな。映画の時は上映時間を指針にしたりする蓮實氏だが、ここでは単行本ごとの1頁の単価を比較したり…それにしたとて主題・観念論から身を捩らせんとする運動としてあるがゆえに刺激的。2016/08/17
罵q
3
時評集。無名性や複数性を希求し、日本文学史の正統からは「外れた」批評を展開する。文芸誌に掲載される中でも一握りの、見るべき語るべきところを持つ、言葉の運動に自覚的な作品/作家を取り出していく。2018/06/05