- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
かつぎ屋婆さん、夜のタウン・ウォッチング。盛り場の生態と変遷を、湯島天神下への行商に生きた一老婆の眼を通して描く、都市民俗学の野心的試み。
目次
1 かつぎ屋フクの商売―都市と農村のつながり(老婆登場;かつぎ屋という仕事;我孫子の家;焼け跡の上野;闇屋の街;警察との鬼ごっこ;裏通りから見る花柳界)
2 芸者桃太郎の転業―盛り場の享楽性(下谷花柳界;芸者のはじまり;人身売買の世界;半玉から芸者へ;芸者と娼妓;下谷花柳界の終焉)
3 ホステス由美の当惑―盛り場の地縁と社縁(天神下の夕暮れ;ピンクサロンの失敗;不動産業者の目から;都市の地縁社会)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なめこ
1
武家エリアと町家エリアの狭間にある湯島天神、その周辺に発生した盛り場。すぐ近くに上野の色街があり、花街としての機能に特化して発展した経緯を、戦後から現代に生きる人々の語りから描く。この土地に根付いた担ぎ屋、芸妓、不動産屋のみならず、どうしても馴染めなかった人の声も収められているのが良い。刊行は1987年。地縁の強い盛り場、という特性は今どうなっているのだろう。空襲の焼け野原から数ヶ月で営業再開するほどなくてはならないものだったのに、疫病蔓延のもとでどうしているだろう。2021/09/11
kassie
1
偶然にも通勤途中なので湯島駅周辺はよく行っていて、そのときに感じた、上野のピンク街ほどではないけど雑多な感じ、それも清潔感を感じるもの、これがなんとなく引っかかっていたとき、図書館にて遭遇した本。神崎先生は宮本常一のお弟子さんで、現在もその豊かな民俗学的知見から様々なアドバイスをいただくことが多々あるが、モノグラフの描き方は、1人のキーパーソンを軸に展開していて、私の書きたい感じの完成形と前から思っている。1人の人間の生き様からその周りの社会を浮き彫りにする、そういう民俗誌を描きたい。2016/09/18
-

- 電子書籍
- 東京郊外のマンションからのまったり異世…
-

- 電子書籍
- スキルポイントが俺をレベルアップさせた…
-

- 電子書籍
- もふもふと楽しむ無人島のんびり開拓ライ…
-

- 電子書籍
- 王様ランキング【単話版】第173話 B…
-
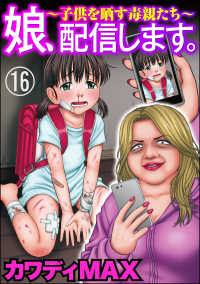
- 電子書籍
- 娘、配信します。~子供を晒す毒親たち~…




