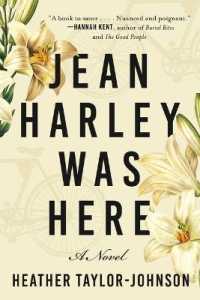出版社内容情報
気候変動に関する理解が時代とともに深まってきた様子を、人々の歴史的冒険に結びつけながら解説していく物語。地球温暖化と変えられた未来を考える教養書。
内容説明
本書では、気候と天候の変動に関する理解が時代とともに深まってきた様子を、その時代を生きた人々の冒険に結びつけながら探っていく。自然現象と地球環境の物語。
目次
シベリアからやってきた―気象学と天候の起源
パタゴニアの海流―マジェランの38日間の冒険
風力10―海賊たちの沈んだ宝石
ハリケーンの強さ―安心できる土地はない
ドロシーの竜巻―大平原のトルネードとサイクロン
最後の大冒険―気球飛行による世界横断
三態変化―雲が流す涙
世界の頂上の征服―雪、吹雪、そして雪崩
不沈艦タイタニック―氷山に引き裂かれた口
モンスーンと強風―死と再生
文明の発祥地―洪水がナイルの谷を肥沃にする
現代の洪水―ミズリー川とミシシッピ川
エル・ニーニョ―不思議な海流
変わりゆく気候―地球温暖化と変えられた未来
著者等紹介
レヴィ,マッシス[レヴィ,マッシス][Levy,Matthys]
世界的な構造事務所であるワイドリンガー・アソシエイトの構造技術者として、アトランタのオリンピック競技場(ジョージア・ドーム)など、世界中の著名な建物の構造設計を行っている。マリオ・サルバドリーの後継者的存在で、その著作には定評があり、設計経験における体験を通じて、数学と科学の基本を中学生に教える教育団体であるサルバドリー・センターの理事を勤めている
望月重[モチズキシゲル]
1931年生まれ。1954年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1962年武蔵工業大学助教授。1967年工学博士。1969年米国コロンビア大学客員研究員。1971年武蔵工業大学教授。2001年武蔵工業大学名誉教授。2007年日本建築学会教育賞(教育業績)受賞
濱本卓司[ハマモトタクジ]
1952年生まれ。1975年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1975年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。工学博士。1986年米国イリノイ大学客員研究員。1990年武蔵工業大学助教授。1996年武蔵工業大学教授。1999年日本建築学会賞(論文)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tuppo