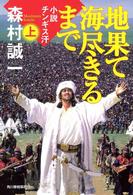内容説明
「冒険遊び場」の原点。都市の子供の遊び場を豊富で自由なものにする、世界中の意欲的な遊び場の実例を集めた本書は、専門家のみならず親世代の関心も呼んだ。子供が人としての生きる力をつける「遊び」の充実とは―、待望の復刻。
目次
1 序論
2 「何々遊び」という名前のない遊び
3 グループ・プレイ
4 冒険遊び場
5 プレイパーク
6 近隣公園
7 特異な環境にある子供
8 身体障害児、情緒障害児、不適応児のための遊び
9 未解決の問題
著者等紹介
アレン・オブ・ハートウッド卿夫人[アレンオブハートウッドキョウフジン][Lady Allen of Hurtwood]
イギリスの造園家、福祉活動家(1897~1976)。イギリス造園学会副会長、イギリス保育学校協会副会長、幼児教育世界機構(OMPE)初代会長、ロンドン冒険遊び場協会長、障害児ホリデイクラブ会長を歴任。1944年に施設児童の生活を告発した単独キャンペーンで、1948年の児童憲章を実現した
大村虔一[オオムラケンイチ]
都市設計家(1938~)。大村虔一+都市デザインワークス、NPO法人日本冒険遊び場づくり協会代表、宮城県教育委員会委員長などを務める。東北大学大学院教授、宮城大学副学長、(財)宮城県地域振興センター理事長などを歴任。世田谷ボランティア協会理事として、「羽根木プレーパーク」の区と住民の協働システムをつくる。都市設計家の仕事として「東京オペラシティ」などがある
大村璋子[オオムラショウコ]
日本への冒険遊び場の紹介者で活動推進者(1940~2008)。IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会)初代日本支部長のかたわら、夫とともに地域住民手づくりの冒険遊び場運営をスタートし、世田谷区と協働の羽根木プレーパーク創設、全国の遊び場づくり運動のきっかけをつくった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- わけありシングルママの再会愛【タテヨミ…
-
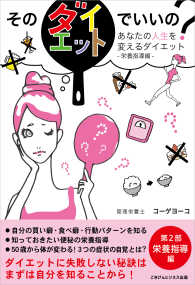
- 電子書籍
- そのダイエットでいいの? あなたの人生…