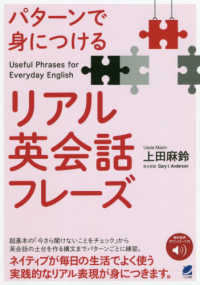内容説明
民族の伝統とその環境に培われた建築の原理。平面はなぜ四角くなったか。柱を立てるのは右廻りか左廻りか。部材の向きは元か末か。エスニックな建築の素朴な空間に、建築の本質を読み解く。
目次
エスノ・アーキテクチュアとは
屋根の材料と勾配の選び方―民族文化と地域の特性
右が先か左が先か―二者択一の原理
末口からか元口からか―部材の向きが及ぼす形態的な特性
建築はなぜ四角になったか1―対角線による柱組
建築はなぜ四角になったか2―円形住居の柱組
建築はなぜ四角になったか3―円錐形から方形の屋根へ
建築はなぜ四角になったか4―四角い土壁の登場
部分から全体へ1―土の建築における型枠の使用
部分から全体へ2―材料を混ぜて積むことの意味
妻入りと平入り―建物の軸と街並みとの関係
エスノ・サインすとエスノ・テクノロジー
著者等紹介
太田邦夫[オオタクニオ]
1935年東京都生まれ。1959年東京大学工学部建築学科卒業、現代建築研究所入社。1961年東京大学教養学部図学教室助手。1966年東洋大学工学部建築学科助教授。1984年東ヨーロッパの伝統的木造建築の研究で工学博士号を取得、同学科教授。2001年ものつくり大学建設技能工芸学科教授。2005年同大学退職、太田邦夫建築設計室主宰。東洋大学・ものつくり大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
モダニズム建築批判の1960年代B・ルドフスキー『建築家なしの建築』展覧会が催された。日本ではアジアをテーマとする80年代に民俗学、人類学、人文地理学を巻き込むエスノ・アーキテクチュア研究が現れる。この研究を主導した著者は本書で、左右の選択、円と四角の平面構成の遷移、屋根の材質(煉瓦、板)や柱等の構法の差異を変数とし、それら差異を生む環境や民族的文脈を通してトポロジカルな展開として世界の民族建築を示す。その過程で技術の発達で失われるエスノ・テクノロジーとそれを支えるエスノ・サイエンスの存在が浮かび上がる。2025/09/26
鵐窟庵
3
本書は世界各地に伝統的な民族建築の構成原理について考察を行なっている。住居に見られる構成や部材の右と左の組み立て方の機能的な意味や社会的な意味の違い、円形と方形の平面構成や屋根構造の違い、煉瓦や版築、井楼組等の伝統構法、幾何学の伝統的な作図法などから、近代・現代建築には見られない建築の原型を見出そうとしている。また著者はエスノ・アーキテクチャを支えるエスノ・テクノロジーがあり、その元にエスノ・サイエンスが基礎付けられるとする。技術が万人を利するためには、こうした簡素で普遍的な構法が今後の建築で重要になる。2019/01/06