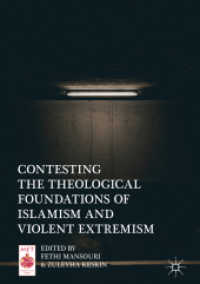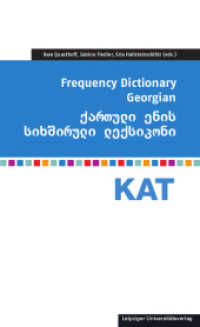内容説明
一本の柱に垂直性を、複数の柱がかこむ間(ま)に水平的展開を見る著者は、優れた日本建築と庭園を渉猟し、その空間の特質を、多彩な美とともに示し、日本人の空間意識や空間意匠における間の重要性を解きあかす。名論文、待望の再録成る。
目次
第1部 日本建築の空間(日本人の空間意識―間;原初的な時間と空間;建築基本空間の拡大;空間の水平的な結合・展開 ほか)
第2部 九間論―農耕集落の核から現代の住居単位まで(『利休の茶室』から;帖と坪、間と間;九間の全盛;主座敷の典型 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
6
身体を入れる器としての建築には心地さが必要であり、その感覚は昔も今も変わらぬ人間の身体の運動と感覚を基準としたその元型が各時代の建築にも残っているはずだ。欧米ではC・アレグザンダーやK・リンチが愛着や心地よさから建築を捉え直したが、著者は3間×3間(5.4m×5.4m)からなる九間(ここのま)の空間を日本建築の基本単位として見出す。大建築が乱立する時代に抗する著者は本書で、九間を4分割した4畳半の広さが日本建築の単位である理由を、仏教渡来以前の大嘗祭の空間、茶室、能舞台等の古建築の空間構成から説き明かす。2025/08/07
YuYu
0
日本建築の空間構成はどういった理由で成り立っているのか。事例を挙げながら様式的、地形的な論点から間(ま)を語る。水平的展開をする日本建築の豊かさを改めて思った。2013/08/15
-
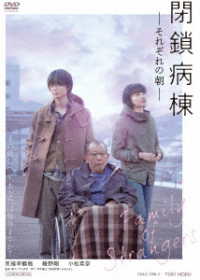
- DVD
- 閉鎖病棟‐それぞれの朝‐
-
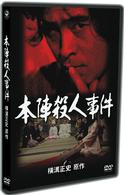
- DVD
- 本陣殺人事件(TV版)