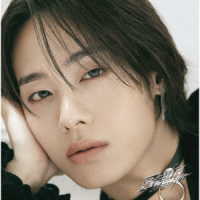内容説明
デジタル革命は、何を変え、どこへ向かうのか?建築の表記法の変遷―アルファベット、図面、そしてアルゴリズム―を辿り、伝統的なハンドメイドと共通する、可変性にもとづくデジタル・エイジの建築を解き明かす。
目次
1 可変性、同一性、微分的差異(建築と同一的なコピー:そのタイムライン;代著と表記法;原作者性;初期近代における同一的な複製の追求;幾何学、アルゴリズム、そして表記法の障害;同一性の衰退;アルベルティ・パラダイムの反転)
2 興隆(アルベルティと同一的なコピー;デジタルへ;ウィンドウズ;I.D.ピクチャーとファクシミリの力;アルベルティの模倣ゲームとそのテクノロジーの欠陥;アルベルティ・パラダイムの発明)
3 衰退(フォーム;スタンダード ほか)
4 エピローグ:スプリット・エージェンシー―建築家の力の分割と移譲
著者等紹介
カルポ,マリオ[カルポ,マリオ] [Carpo,Mario]
ロンドン大学バートレット建築スクール教授(建築史)。建築理論、文化史、そしてメディアや情報テクノロジーの歴史の間の関係に焦点を当てた研究と執筆を行っている
美濃部幸郎[ミノベユキオ]
一級建築士、博士(工学)。美濃部幸郎アトリエにて、自然のかたちと、コンピュータによる人工物のデザインの関係を追求している。さらに建築のタイポロジーの研究も行ってきている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ONE_shoT_
1
1990年代以降のデジタル・テクノロジーが建築にもたらす革命について論じられた一冊。著者は建築を、建築を構想すること、実際に建設されるもの、それらをつなぐ情報技術から成るものと捉えている。中世の建築は、多くの職人によるハンドメイドのものだったため「可変性」を有していたが、ルネサンス期の図面による表記法と印刷技術により、建築は規格化された図面から複製される「同一性」を有するに至った。しかし、あらゆるものを変数として捉え、変数を管理するデジタルなアルゴリズムが、建築に再び「可変性」をもたらしている。2020/05/16
RS
0
デジタルテクノロジーによりもたらされるデザインの作者の二階層性、結果物の可変性などの特徴と中世の職人の世界のそれらとの類似性を指摘し、これからの作者への課題が投げかけられている。後書きでは、モデル(暫定的に詳細が決定されたもの)とタイプ(未規定な点が多く、抽象度が高いが、「類」の起源となりうるもの)を区別しつつ、タイポロジーを時の審査を受けて降り積もった、人工物による文化的な歴史と定義した上で、タイポロジー論とデジタルデザインのプロセスとの関係性が今日的課題として指摘されているのが興味深い。2016/01/28
YuYu
0
現代のデジタルツールの役割を15世紀に起きたアルベルティの理論から始まる建築家の役割から論じている。 主に1990年代に起きたデジタル革命の位置づけを説明し、現在までの流れを論じている。 著者の書いた「The Digital Turn in Architecture 1992-2010: AD Reader」がこの本を補完的に説明している。2014/10/20
引用
0
面白かったのだが、デジタルテクノロジーが原作者性を解体する、というのは、デジタルテクノロジーのなかでは伝統的な原作者性はオブジェクトではなくオブジェクティルの原作者に対応する、と言っているに過ぎない部分がある。そんなことを言い出したら、というのはあれだけれど古典的な「様式」がオブジェクティルに相当すると言ったほうがよくわかる2021/01/07
kook9
0
近代以前の時代であるルネサンス期前後から産業革命を経て、現代のデジタルテクノロジーの時代までの建築史を表記法の観点から記した本である。建築家がこれまで何百年も守り続けてきた、建築物のデザインの"原作者"性がアルゴリズムによるデジタルテクノロジーを用いた表記法によって消失しようとしている。しかしそれは近代以前の手工職人的な建築時代にあったアノニマスな性質と重なる部分がある。2018/03/19
-
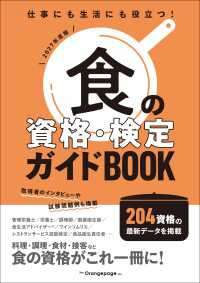
- 電子書籍
- 食の資格・検定ガイドBOOK 2027…