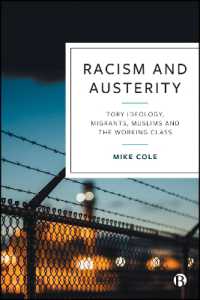内容説明
なぜ、コルビュジエの建築に惹かれるのだろうか?「白の時代」以降の主要住宅12をとりあげ、その空間構成法を解き明かす。そこには建築的散策路が織りなす空間の詩法が読み取れる。ル・コルビュジエ研究の決定版。
目次
第1章 建築―その変容に満たされた不変の形式
第2章 ル・コルビュジエの12の住宅の空間構成(ラ・ロッシュ/ジャンヌレ邸;クック邸;テルニジアン邸;母の家;ガルシュの住宅 ほか)
第3章 主体の複数性―ル・コルビュジエと現代
著者等紹介
富永譲[トミナガユズル]
建築家。1943年奈良県出身。1967年東京大学建築学科卒業後、菊竹清訓建築設計事務所入所。1972年富永譲+フォルムシステム設計研究所設立。1973‐9年東京大学助手。2002年法政大学教授。「茨城県営長町アパート」(2001年日本建築学会作品選奨)、「ひらたタウンセンター」(2003年日本建築学会作品賞受賞)などの作がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
14
「空間」が気になっている。ル・コルビュジエは、90年くらい前に、住宅に「空間」を織りこんでいて、それを<建築的散策路>と呼んだ。たとえば「人が入ると建築的な光景がつぎつぎと目に映ってくる。巡回するに従って場面は極めて多様な形態を展開する。流れ込む光のたわむれは壁を照らし、あるいは薄暗がりをつくり出す。」もう一つ、「この家の場合、本当に建築的な散歩によって、次々と変わった予期しない、時に驚くべき姿を呈するのだ。例えば構造的には柱梁の絶対的な規格を持ちながら、そこにこれだけの変化が得られるというのは面白い。」2017/09/29
鵐窟庵
7
ル・コルビュジェの住宅にみる空間構成の把握が本書の主題である。ドミノシステムによる水平性の強調、構成単位の反復、立体の相互貫入など、基本的な構成方法が本書で取り上げられた12の住宅から、明らかになるが、いずれも単なる手法の適応ではなく、全体の秩序と部分の要素の衝突によるその都度発見されうる設計プロセスであり、そこにル・コルビュジェの分かりやすいようで判然としない、しかしそれが豊かな体験をもたらす空間の本質が見出される。それを追体験するには本書に付属している多くの図面や写真を十分に読み込んで行く必要がある。2019/05/05
ぶらり
5
読書とは、自分の思考や嗜好の特性を確認することと、47歳を目前にして分かった気がしている…最新の自己満足。昨夏の夏目漱石以来、読書を貪ることで若い頃には自信すら持っていた自分の芸術性?を再起動し、感性の赴くまま、ニーチェやドスト、ボルヘスやマルケス、そしてオルハン、平静を装いつつも実は自分の「不足」に焦燥しつつ這いずり回る気分。そしてそこでは「憂愁」、トスカ、ヒュズン、厭世や円環が自分を揺さぶるのだった。傍らのモダン建築、建築とは何の縁も無い自分を魅了するのも「憂愁」なのだと昨夜この本を開いて理解した。2011/04/01
尋日
1
読んでいるうちに、我が母校の校舎を連想した。そういえば、母校のデザインは丹下健三の弟子がデザインしたとか母校の先生が誇らしげに語っていたのを思い出したで、ちょっと調べてみたら、やはり丹下はル・コルビュジエから強烈な影響を受けていた。卒業して15年くらい経って初めて気付いたわ。2012/10/29
-

- 洋書
- freebleeding
-

- 電子書籍
- ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠…