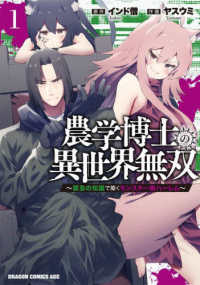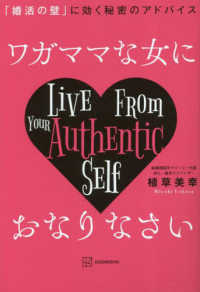出版社内容情報
近年の災害事例及び地形地質学の知見を踏まえ、地すべり・山くずれ・斜面崩壊等に関する専門基礎的な内容を多面的に解説する。
目次
日本における地すべり・山くずれの背景
岩石の種類と地すべり
地すべり地形と微地形
山くずれの諸現象
風化作用
風化を進める岩石の構造
岩石の風化速度
山地斜面の構造と動き
斜面崩壊に関わる水
地すべりに関わる粘土鉱物
植物と地すべり・山くずれ
農林業と地すべり
著者等紹介
高谷精二[タカヤセイジ]
農学博士(北海道大学)。1942年徳島県に生れる。1965年愛媛大学農学部林学科卒業。1968年北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。1972年南九州大学園芸学部。2008年南九州大学環境造園学部教授、定年退職。現在、宮崎応用地質研究会会長、南九州大学環境造園学部非常勤講師。受賞:「平成5年鹿児島集中豪雨」(NHK映像ニュース賞金賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
34
読み友さんのコメントから。日本の国土のほとんどが山林であるため、土砂災害はインフラや住環境への大きな脅威である。基本的には、崩落のあとに植生は復活し、また長い年月のうちに水・植物・(動物)の影響を受けて崩落が起こるということは自然のサイクルであること、崩れやすい土壌・地層があること、降雨量の多い日本では水が崩落に大きな影響を与えるらしいことまではわかったが、本格の専門書のため歯が立たず。これでは埒があかないので、同じ著者の入門書にさかのぼって再チャレンジ。文中の手描き説明図が素朴で妙にかわいらしくて佳き。2022/06/20
アナクマ
26
土砂災害は、山中でも都市部でも起こる(65年までは山地災害と呼称されていた)。稀にしか被災しない、とは言いきれず、科学技術でリカバーできる余地は少ない。だからこそ、この地面の挙動を知りたい。◉というわけで、カラー口絵の災害の規模感に目を見張る。図表はたくさんあるけど専門的で難しい。土壌の三相、面白い。奇跡の一本松は樹高28m、根広8m、根深2m。11-12章_植物・農林業との関係性の記述には要注意。◉岩石の風化速度。凝灰岩は10年で数ミリ。花崗岩は1000年で数ミリ。→2022/05/22
くらーく
3
崖崩れ、山崩れ、地すべり、土石流と日本では分類されているそうな。いやー、まったく意識したことはありませんでした。 地すべりと山くずれに分類され、山くずれが表層と深層に分類されるそうな。 地すべりの方が山くずれより、移動規模が大だそうで。 今度からニュースを見るときの参考になりそうだ。 写真を眺めて、平地に暮らしているありがたさを、しみじみ感じていました。ありがたやま。2025/10/17
-

- 和書
- 本物のコンサルを選ぶ技術
-
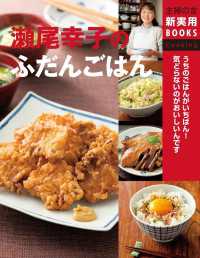
- 電子書籍
- 瀬尾幸子のふだんごはん 主婦の友新実用…