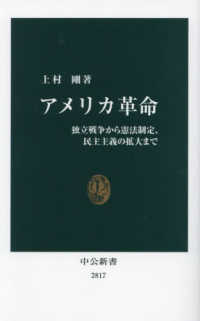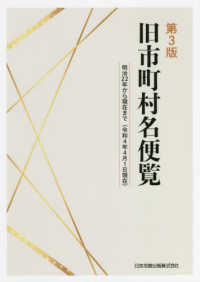内容説明
人びとの関心を喚起する未知の学域は、なお豊かに存在する。日本文学とその研究がこれまでに担ってきた領域、これから創造していく可能性をもつ領域とは何か。人文学としての文学が人間社会に果たしうる役割に関して、より豊かな議論を成り立たせるには、これからどうしていけばよいのか。日本文学の窓の向こうに広がるものの総体を捉えようとするシリーズ第4巻。
目次
総論―往還と越境の文学史にむけて
第1部 文学史の領域(“環境文学”構想論;古典的公共圏の成立時期 ほか)
第2部 和漢の才知と文学の交響(紫式部の内なる文学史―「女の才」を問う;『浜松中納言物語』を読む―思い出すこと、忘れないことをめぐって ほか)
第3部 都市と地域の文化的時空(演戯することば、受肉することば―古代都市平安京の「都市表象史」を構想する;近江地方の羽衣伝説考 ほか)
第4部 文化学としての日本文学(反復と臨場―物語を体験すること;ホメロスから見た中世日本の『平家物語』―叙事詩の語用論的な機能へ ほか)
著者等紹介
小峯和明[コミネカズアキ]
1947年生まれ。立教大学名誉教授、中国人民大学高端外国専家、早稲田大学客員上級研究員、放送大学客員教授。早稲田大学大学院修了。日本中世文学、東アジア比較説話専攻。物語、説話、絵巻、琉球文学、法会文学など
宮腰直人[ミヤコシナオト]
山形大学准教授。語り物文芸、お伽草子、物語絵画専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。