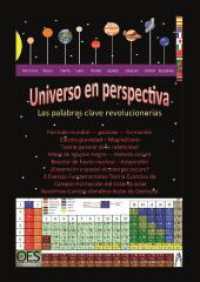出版社内容情報
物語の中の音楽はどのような役割を果たしているのか
ある一定の文化が固定した社会の中では、
同じ解釈を最低限の了解として享受し、
お互いに評価し合うことが可能である。
物語が享受されていた社会において、
音楽にはどのような体勢、モードが
求められていたのか、
その時代的な変化などを解き明かす。
『とりかへばや』『狭衣物語』『うつほ物語』
『源氏物語』などの物語に書かれた
古代歌謡『催馬楽』の表現を考察。
凡例
はじめに 物語に引用される音楽
第一章 物語における音楽表現
第一節 物語と歌謡
第二節 唐楽から雅楽へ
第三節 物語と音楽
第二章 物語に現れる歌
第一節 人生の転換―『とりかへばや』と催馬楽
第二節 歌の題を名付けられた女の人生―『狭衣物語』と催馬楽
第三節 人間関係を表出―『うつほ物語』と催馬楽
第四節 像を与える歌と祝福の歌―『浜松中納言物語』、『夜の寝覚』と催馬楽
第三章 恋愛と歌
第一節 宴と歌謡―催馬楽と場の意識
第二節 繁栄をたたえる歌―催馬楽「此殿」
第三節 予言する歌・童謡―『続日本紀』に見る催馬楽の原型歌
第四章 歌で示す物語の主題と記憶―『源氏物語』と催馬楽
第一節 タブーを抱える歌
第二節 場に意味を与える
第三節 記憶を呼び戻す
第四節 一族と歌謡
第五節 『源氏物語』と催馬楽
第五章 記録された催馬楽
第一節 催馬楽を書く『枕草子』、書かない『枕草子』―『枕草子』と催馬楽、諸本比較
第二節 和様化した歌の言葉―平安朝文学と総角
結び 物語において音楽(歌謡)が導く表現とは
あとがき
参考文献リスト
索引―書名・人名・事項
山田 貴文[ヤマダ タカフミ]
著・文・その他
内容説明
ある一定の文化が固定した社会の中では、同じ解釈を最低限の了解として享受し、お互いに評価し合うことが可能である。物語が享受されていた社会において、音楽にはどのような体勢、モードが求められていたのか、その時代的な変化などを解き明かす。『とりえへばや』『狭衣物語』『うつほ物語』『源氏物語』などの物語に書かれた古代歌謡『催馬楽』の表現を考察。
目次
第1章 物語における音楽表現
第2章 物語に現れる歌
第3章 恋愛と歌
第4章 歌で示す物語の主題と記憶―『源氏物語』と催馬楽
第5章 記録された催馬楽
結び 物語において音楽(歌謡)が導く表現とは
著者等紹介
山田貴文[ヤマダタカフミ]
1985年生まれ。立正大学文学部文学科日本語日本文学専攻コース卒業。2016年立正大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程修了。同年、博士(文学)号取得。都内私立高校非常勤講師を経て、立正大学文学部文学科に勤務。助教。専門は、古代文学および物語文学と歌謡文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。