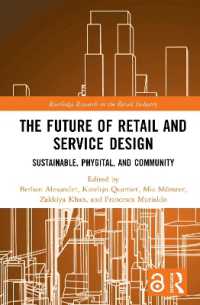出版社内容情報
古典・古文が苦手だと思っているあなたへ語り継ぐ、古典文学の世界。
古典文学の魅力を伝えたくてたまらない研究者と、生徒を前にして、古文の面白さや学ぶ意義をわかってもらおうと日々奮闘している、現場教員たちとのコラボレーションで贈る前代未聞の本。研究者の本気と現場の教師の本気で、古典の魅力を届けます!
[本書の読み方]
○中世文学の研究者たちに教育現場からの問いかけに答えるつもりで、教材研究の新しい視点を書いてもらいました。
○第1部では、中世文学をジャンル別にとりあげ、第2部は、時代・宗教・文法・教科書と四つのテーマを設けて論じています。
○毎日、生徒たちの真剣な視線を浴びながらひるまず教壇に立つ方々には、生徒に答えるつもりでコラムを書いてもらいました。
○どこから読んでもかまいませんが、通して読めば、おのずと全体のつながりがみえてくるでしょう。語り継ぐ中世文学史です。
○古典教育の現場の方のみならず、老若各世代の方々にお読み頂ければと思っています。
執筆者は、小助川元太/伊東玉美/霧林宏道/谷 知子/吉野朋美/花部英雄/三浦 敦/平野多恵/安村史子/牧野淳司/清水由美子/松尾葦江/出口久徳/今井正之助/谷口耕一/中野貴文/深沢眞二/須賀可奈子/山中玲子/石井倫子/秋田陽哉/姫野敦子/小助川元太/永濱知寿子/松薗 斉/藤巻和宏/冨澤慎人/吉田永弘/日下田ゆず/須藤 敬/渡辺登紀子。
【 私たちがこの本を読んでほしいのは、
〇古文嫌いの生徒に古文の魅力を伝えたいと考えている中学校や高校の国語の先生。
〇古文の授業のネタがほしいと思っている国語の先生。
〇中学校・高校の国語の免許を取りたいと考えている人。
〇古文は苦手だったけれど、少し勉強してみようかなと思っている大人。
〇古文の授業は面白くないと思っている高校生。
そして、
〇「古文なんて面白くない」と思っているのに、なんとなく気になってしまい、本を手に取ってしまった、あなたです。
最初から読む必要はありません。目次を見て、気になったところから読んでもらってけっこうです。そして、ぜひ古文=古典文学の面白さを発見してほしいと思います。】
「古文は面白くない」って本当ですか?―本書を手にとってくださったあなたに(小助川元太)
第1部 どこが面白いのか?―中世の古典たち
1 世俗説話(伊東玉美)
亀の恩返しと絵仏の帰還
【古典は、当時の価値観に寄り添って理解する必要があるナイーブな側面と、現代にも通じる切り口で直接アプローチできるシャープな側面の、両方を持っている。】
1 はじめに/2 亀の恩返し/3 絵仏の帰還/4 両話に共通するもの/5 おわりに
コラム 教師に必要なことは(霧林宏道)
2 和歌(谷 知子)
恋の歌の力―『百人一首』の魅力
【『百人一首』の最大の魅力は何かと聞かれたら、私は「美しい型」だと答えたい。だからこそ、さまざまな豊かな広がりを持つ文化が生まれたのだと思う。】
1 恋の歌の意味/2 序詞・掛詞/3 命をかけた恋/4 題詠/5 恋の歌の力
3 西行・長明(吉野朋美)
西行と長明―乱世を生きたふたりの出家者
【両者は私たちの前にそれぞれの作品で別個に姿を見せているようだが、そのふたりの生きた時代も見つめるものも重なっている。】
1 はじめに/2 西行・長明の姿勢―福原遷都を例に/3 当時の世相とふたりの社会的関心/4 勅撰和歌集への入集に関連して/5 長明における西行/6 おわりに
4 伝承の人物像(花部英雄)
愛好する人々と共に生きる「人物像」―西行と義経
【伝承の人物像は社会や時代の動きと密接に関連して形成される。伝承は文字等により記録されることが少ないため、常に現在の伝承という形で人々の関心や動向を反映しながら揺曳していく。】
1 流動的な「伝承の人物像」/2 西行と義経の時代/3 この時代の社会と文学はどう考えられてきたか/4 西行のイメージ形成―一部の裕福な知識層の間で/5 西行のイメージ形成―一般大衆の間の真逆の西行像/6 義経伝説と時代気運/7 おわりに
コラム 古典の「事実」に学ぶ(三浦 敦)
5 明恵(平野多恵)
人生を変えた神のお告げ―鎌倉時代のノンフィクション文学『明恵上人神現伝記』
【八百年前にも、人や社会のありようにはドラマがありました。それを後世に伝えようとする想いに駆られた人がいたからこそ、私たちは当時の人々の息吹をいきいきと感じることができるのです。】
1 はじめに/2 自分の道を求めて/3 インドへの思い/4 春日明神の降臨/5 春日明神との対話/6 二度目のインド巡礼計画/7 おわりに
コラム 額の裂けた地蔵の話(安村史子)
6 仏教説話(牧野淳司)
笑いと涙の中世寺院―仏教説話を生み出す場
【仏教を弘めるための文学と決めつけてしまうのではなく、笑いと涙を活力源として生きた人々が僧侶とともに作り上げた文学として、仏教説話の領域を見つめ直したい。】
1 はじめに/2 「狂惑の法師」/3 仏事での笑い/4 演戯する説経師/5 おわりに
コラム 教室で軍記文学を読むということ(清水由美子)
7 平家物語(松尾葦江)
眼で聴き、脚で見る―平家物語を読んでみよう
【この物語の中には戦争だけでなく、じつに多様な人生が、生き抜くとはどういうことなのかを、あたかも私たちに問うように描かれている。】
1 宇宙から地上へ、永遠から今へ/2 歴史文学の手口/3 死者への想い/4 ことばのちから/5 平家物語は戦争文学なのか
コラム 「役に立つ」古文(出口久徳)
8 太平記(今井正之助)
“やりきれない”話―高師泰の悪行とその被害者
【やりきれない、ひどい事件・事態は今も形をかえて現実に起こっている。これを教材としてとりあげ議論する意義があるのではないか。】
1 はじめに/2 本文/3 教材試案
コラム 古典なんて(谷口耕一)
9 徒然草(中野貴文)
背を向ける狛犬とすれ違う対話
【学生たちは、古典はすばらしいもの(らしいの)だが自分たちとは関係の無い何かだと思っているのかもしれない。自由に触れて楽しんで構わない「古典」と思えるにはどうすればよいか。】
1 話が噛み合わない/2 空気が読めない/3 古典文学は、遠い日の花火ではない
10 座の文芸(深沢眞二)
想像力のあそび―連歌
【連歌でなら、どこへでも行けるし、どんな時間にも飛べるし、どんな心境でも知ることができるし、どんな身分にもなれる。連歌は、貴族から武士階級や庶民までが作者となった熱狂を伴う大衆的文芸でした。はたして何が人々を熱狂させたのでしょうか。】
1 「手の舞ひ足の踏む所を知らず」/2 「雪牧両吟住吉百韻」の六句を読む/3 「四季の庭」体験装置
コラム 「なぜ古典を学ぶのか」―授業の中から考えたこと(須賀可奈子)
11 世阿弥(山中玲子)
詩人は最高の教師でもあった
【世阿弥が経験から絞り出すように語る言葉は、人生論としても心に響く普遍性を持っている。また、能のテキストのイメージは、自由に想像を膨らませる余地を多分に持っている。世阿弥の紡ぐ言葉の魅力に迫る。】
1 世阿弥の能楽論/2 世阿弥の能
12 狂言(石井倫子)
人間だもの、夫婦だもの―狂言〈鎌腹〉
【狂言の登場人物は、皆どこか憎めない。極悪人がいないところも魅力だろう。人間、生きていればいろいろな失敗がある。それを笑い飛ばしてしまう、狂言はそんな人間賛歌のドラマなのだ。】
1 ユニバーサルな笑い/2 〈鎌腹〉を読む(1)/3 〈鎌腹〉を読む(2)/4 〈鎌腹〉を読む(3)
コラム 高校生が感じることばの変化(秋田陽哉)
13 歌謡(姫野敦子)
室町時代の空気は読めるのか?―『閑吟集』の挑戦
【文字による記録しか手段のない時代には、音や声の多くが消えてしまい不完全な記録しか残らない。室町時代の「小歌」から当時の空気をどれだけ引き出すことが出来るのか。】
1 第一回 『閑吟集』一八番歌・一九番歌から/2 第二回 五五番歌をめぐって/3 第三回 「世間」の感覚―四九番歌・二三一番歌をめぐって/4 第四回 真名序・仮名序
14 御伽草子(小助川元太)
室町時代を遊んでみよう―御伽草子『ものくさ太郎』を読む
【御伽草子は、夜の退屈な時間を楽しむための「おとぎ」という行為から生まれた言葉で絵入りの短編物語のこと。だがこの物語には、退屈しのぎだけではなく、読んだり語ったりすることで、幸せを呼ぶ力もあったのだ。】
1 御伽草子とは何か/2 ものぐさも徹底すればツキを呼ぶ―太郎と地頭の問答/3 なぞなぞは室町時代のコミュニケーション―太郎と女房の問答/4 和歌が詠めると得をする―女の心を動かした太郎の和歌の力/5 祝言としての大団円―御伽草子の読まれ方
コラム おれ古典いらないんだけど(永濱知寿子)
第2部 もっと広がる面白さ―時代・宗教・文法・教科書
1 時代(松薗 斉)
中世の古典作品にみえる女房
【鎌倉時代に作られた王朝の世界を舞台とした文学作品は『源氏物語』とよく似ているけれど、一〇〇年も二〇〇年も時間的に隔たっているのに同じような人たちと説明してよいのかどうか。中世の女房たちの歴史的背景を少し違った視点から検討する。】
1 はじめに/2 女房の人数/3 女房の身分/4 おわりに―女房文学の行方
2 宗教思想(藤巻和宏)
古典教育と宗教思想―中世は「宗教の時代」なのか?
【「わかりやすく」説明する際の常套句、 中世は宗教の時代――。果たしてそれは本当の中世を言い当てているのだろうか。教科書収載作品から中世宗教の基礎知識を解説する一方で、時代の「特徴」なるものを見いだすことの“功罪”についても考える。】
1 時代のイメージ/2 北野天神から見る神仏習合の諸相/3 観音の霊験と夢/4 古代と中世の連続性
コラム 「薩摩守忠度といふ人ありき」は誰の経験か(冨澤慎人)
3 文法(吉田永弘)
文法が分かると何が分かるか
【古典の読解という、過去と現在のことばを往還するダイナミックな営みが面白くないはずがない。古典を読んでいると、文法書や辞書に記載された内容では説明がつかない例に必ず出会う。その面白さを伝えてみたい。】
1 文法は嫌われる/2 嫌われる理由/3 文法を学ぼう/4 次の世代へ
コラム 先生、文法を勉強すると古典が嫌いになるって本当ですか?(日下田ゆず)
4 中高教科書の古典教材(須藤 敬)
国語教科書での古文教材の扱われ方の現状と課題―小式部内侍「大江山の歌」説話を例に
【心情読解が教室における学習の定型となっている実情を踏まえるなら、そのことに研究サイドがいかに寄与できるのだろうか。二〇一六年度、採録教科書数で上位五位に入る小式部内侍の「大江山の歌」の説話から考える。】
1 授業実践の要となり続けている「心情読解」/2 「学習の手引き」にそって考えてみる/3 次世代に古典をつなぐために
コラム 紙の本はなくなりますか?(渡辺登紀子)
付録資料
・二〇一六年度 中学校・高等学校国語教科書採録 中世文学作品一覧(須藤 敬)
・主な中世説話集一覧(編集部)
教師の宿題―あとがきに代えて(松尾葦江)
松尾 葦江[マツオ アシエ]
1967年、お茶の水女子大学文教育学部卒。1974年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。その後、鳥取大学教育学部助教授、椙山女学園大学人間関係学部教授、宇都宮大学教育学部教授などを経て、2002年から2014年まで國學院大学文学部教授。2003年から2007年まで放送大学客員教授も兼任。1997年、博士(文学)号取得。専門は中世日本文学、特に軍記物語。
著書は、『平家物語論究』(明治書院、1985年)、『軍記物語論究』(若草書房、1996年)、『軍記物語原論』(笠間書院、2008年)などがある。
編著に『海王宮 ―壇之浦と平家物語』(三弥井書店、2005年)、『延慶本平家物語の世界』(栃木孝惟と共編、汲古書院、2009年)、『文化現象としての源平盛衰記』(笠間書院、2015年)など。
小助川 元太[コスケガワ ガンタ]
愛媛大学教授。著書:『行誉編『?嚢鈔』の研究』(三弥井書店)、『月庵酔醒記』(上)(中)(下)(共著、三弥井書店)など。
伊東 玉美[イトウ タマミ]
白百合女子大学教授。著書:『新版発心集 上・下』(浅見和彦と共訳注、KADOKAWA)、『むかしがたりの楽しみ 宇治拾遺物語を繙く』(NHK出版)など。
霧林 宏道[キリバヤシ ヒロミチ]
栃木県立石橋高校教諭。論文:「『扶桑略記』における『日本霊異記』説話の享受」(『國學院雜誌』一一四巻十一号、二〇一三年)、「景戒の『日本霊異記』編纂姿勢」(『伝承文学研究』五五号、二〇〇六年)など。
谷 知子[タニ トモコ]
フェリス女学院大学教授。著書:『和歌文学の基礎知識』(角川選書)、『百人一首(全) ビギナーズ・クラシックス日本の古典』(角川ソフィア文庫)など。
吉野 朋美[ヨシノ トモミ]
中央大学教授。著書:『後鳥羽院とその時代』(笠間書院)、『西行全歌集』(共著、岩波文庫)、『まんがでわかる 日本の古典大事典』(監修、学研プラス)など。
花部 英雄[ハナベ ヒデオ]
國學院大學教授。著書:『西行伝承の世界』(岩田書院)、『漂泊する神と人』(三弥井書店)、『西行はどのように作られたのか 伝承から探る大衆文化』(笠間書院)など。
三浦 敦[ミウラ アツシ]
鳥取県立八頭高校教諭。
平野 多恵[ヒラノ タエ]
成蹊大学教授。著書:『明恵―和歌と仏教の相克』(笠間書院)、『完全解説付き 歌占カード 猫づくし』(夜間飛行)など。
安村 史子[ヤスムラ フミコ]
富士見中学高等学校教諭。論文:「『讃岐典侍日記』の世界」(女流日記文学講座 第四巻『更級日記・讃岐典侍日記・成尋阿闍梨母集』勉誠社)など。
牧野 淳司[マキノ アツシ]
明治大学教授。著書:『延慶本平家物語全注釈(巻一~巻十)』(共著、汲古書院)、『真福寺善本叢刊 東大寺本末相論史料』(共著、臨川書店)など。
清水 由美子[シミズ ユミコ]
清泉女子大学非常勤講師。著書:『校訂 延慶本平家物語』(十二)(共編、汲古書院)、「資料としての軍記文学、物語としての軍記文学」(『國學院雜誌』一一四巻十一号、二〇一三年)など。
出口 久徳[デグチ ヒサノリ]
立教新座中学校・高等学校教諭。著書:『平家物語を知る事典』(共著、東京堂出版)、『図説 平家物語』(共著、河出書房新社)など。
今井 正之助[イマイ ショウノスケ]
愛知教育大学名誉教授。著書:『『太平記秘伝理尽鈔』研究』(汲古書院)、『太平記秘伝理尽鈔1~4 東洋文庫』(共著、校注、平凡社)など。
谷口 耕一[タニグチ コウイチ]
元県立桑名西高校教諭。著書:『校訂 延慶本平家物語』(三)、(九)(編著、汲古書院)など。
中野 貴文[ナカノ タカフミ]
東京女子大学准教授。著書:『大学生のための文学レッスン 古典編』(共著、三省堂)、「『徒然草』「第一部」と光源氏」(『日本文学』二〇一〇年六月号)など。
深沢 眞二[フカサワ シンジ]
和光大学教授。著書:『風雅と笑い 芭蕉叢考』『旅する俳諧師 芭蕉叢考 2』(清文堂出版)、『連句の教室 ことばを付けて遊ぶ』(平凡社新書)など。
須賀 可奈子[スガ カナコ]
法政大学第二中・高等学校教諭。論文:「『平家物語』における異国説話について」(法政大学第二中・高等学校研究委員会編『研究と評論』第七十七号、二〇一二年)など。
山中 玲子[ヤマナカ レイコ]
法政大学能楽研究所所長・教授。著書:『能の演出 その形成と受容』(若草書房)、『能を面白く見せる工夫 』(共著、檜書店)、『人生をひもとく 日本の古典』(共編、岩波書店)など。
石井 倫子[イシイ トモコ]
日本女子大学教授。著書:『風流能の時代―金春禅鳳とその周辺』(東京大学出版会)、『能・狂言の基礎知識』(角川学芸出版)など。
秋田 陽哉[アキタ ヨウヤ]
学校法人滝学園教諭。論文:「源平盛衰記に見られる命令を表す「べし」」(『文化現象としての源平盛衰記』笠間書院)など。
姫野 敦子[ヒメノ アツコ]
清泉女子大学准教授。論文:「『閑吟集』 卯の花襲の小歌」(『国文学 解釈と鑑賞』七〇巻十二号、二〇〇五年)、「中世文学における死と救済 怪異の視点から、能「鵺」をめぐって」(『清泉女子大学人文科学研究所紀要』三十六号、二〇一五年)など。
永濱 知寿子[ナガハマ チズコ]
元杉並学院中学高校教諭。
松薗 斉[マツゾノ ヒトシ]
愛知学院大学教授。著書:『日記の家―中世国家の記録組織』(吉川弘文館)、『王朝日記論』(法政大学出版局)、『日記で読む日本中世史』(共編、ミネルヴァ書房)など。
藤巻 和宏[フジマキ カズヒロ]
近畿大学准教授。著書:『聖地と聖人の東西―起源はいかに語られるか―』(編著、勉誠出版)、『近代学問の起源と編成』(編著、勉誠出版)など。
冨澤 慎人[トミザワ マコト]
普連土学園中学校・高等学校教諭。著書・論文:「夏引の糸―『今物語』第八話を読み解くために」(『二松学舎人文論叢』第六十四輯、二〇〇〇年)、『信実朝臣集 注解』(『普連土学園研究紀要』一五~一九号、二〇〇九~二〇一三年)、『高校日本史に出てくる歴史有名人の裏話』(共著、新人物往来社文庫)、『吉川英治事典』(分担執筆、勉誠出版)など。
吉田 永弘[ヨシダ ナガヒロ]
國學院大學教授。論文:「平家物語と日本語史」(『説林』六〇号、二〇一二年)、「「る・らる」における肯定可能の展開」(『日本語の研究』九巻四号、二〇一三年)など。
日下田 ゆず[ヒゲタ ユズ]
栃木県立茂木高等学校教諭。論文:「「舞姫」におけるアニマシオンの実践―小説を様々な方法で読み、「確かな読み」を実感する―」(研究紀要『しらかし』第九号、二〇〇六年)など。
須藤 敬[スドウ タカシ]
鶴見大学客員教授。著書:『古文教材の考察と実践―教育と研究のフィールドをつないで』(おうふう)など。
渡辺 登紀子[ワタナベ トキコ]
大妻多摩中学高等学校・司書教諭。著書:鈷訓和謌集聞書研究会編『鈷訓和謌集聞書』(共著、笠間書院)など。
内容説明
古典文学の魅力を伝えたくてたまらない研究者と、生徒を前にして、古文の面白さや学ぶ意義をわかってもらおうと日々奮闘している現場教員たちとのコラボレーション。
目次
第1部 どこが面白いのか?―中世の古典たち(世俗説話・亀の恩返しと絵仏の帰還;和歌・恋の歌の力―『百人一首』の魅力;西行・長明・西行と長明―乱世を生きたふたりの出家者;伝承の人物像・愛好する人々と共に生きる「人物像」―西行と義経 ほか)
第2部 もっと広がる面白さ―時代・宗教・文法・教科書(時代・中世の古典作品にみえる女房;宗教思想・古典教育と宗教思想―中世は「宗教の時代」なのか?;文法・文法が分かると何が分かるか;中高教科書の古典教材・国語教科書での古文教材の扱われ方の現状と課題―小式部内侍「大江山の歌」説話を例に)
著者等紹介
松尾葦江[マツオアシエ]
1967年、お茶の水女子大学文教育学部卒。1974年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学。その後、鳥取大学教育学部助教授、椙山女学園大学人間関係学部教授、宇都宮大学教育学部教授などを経て、2002年から2014年まで國學院大学文学部教授。2003年から2007年まで放送大学客員教授も兼任。1997年、博士(文学)号取得。専門は中世日本文学、特に軍記物語(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 導引口訣鈔 - 現代語訳