内容説明
書物の出版、検閲、流通、保存は、読者の歴史とどうかかわってきたのだろうか。現在とは異なる時間、異なる場所の、読者や読書へ―。読者、読書の歴史をどうやって調べ、学んでいけばいいか。何のためにそれを学び、そこからどういうことが分かるのか。読書の歴史についての学び方、調べ方を考える書。
目次
第1章 読書を調べる
第2章 表現の中の読者
第3章 読書の場所の歴史学
第4章 書物と読者をつなぐもの
第5章 書物が読者に届くまで
第6章 書物の流れをさえぎる
第7章 書物の来歴
第8章 電子メディアと読者
第9章 読書と教育
第10章 文学研究と読書
著者等紹介
和田敦彦[ワダアツヒコ]
1965年、高知県生まれ。1994年、早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。1996年、信州大学人文学部助教授、2007年、早稲田大学教育・総合科学学術院准教授、2008年、同教授。1997年、早稲田大学博士号(課程、文学)取得。2005年、コロンビア大学客員研究員、2011年から12年にかけて早稲田大学図書館副館長。2013年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員教授。著書に『書物の日米関係』(新曜社、2007年、日本図書館情報学会賞、日本出版学会賞、ゲスナー賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
35
最近、紙の本が押され気味になっていると感じますが、このような本を出してくれることによって本来の読者が戻ってくれることを期待しています。読者と書物についての歴史をかなり分析しておられ、電子メディアについても書かれています。とくに明治期のことを書かれた部分はかなり資料を渉猟したのでしょう。非常にいい本だと思います。2014/12/06
1.3manen
23
読書は、書物が読者にたどりつき、理解されていく一連のプロセス(013頁)。また、情報を受け取り、理解していく一連の過程(015頁)。書物と読者をつなぐ経路の研究が不十分(017頁)。だからこそ、私は読書ショーアンケートをとっているところ。読書の制約こそ、意識することこそ、読書の可能性を押し広げていくことにつながる(021頁)。読書を通して、いかに読者の不自由さが作り出されていくかが問題(035頁)。2015/01/07
きいち
22
素晴らしい地図。◇冒頭のベトナムの図書館の日本語蔵書との出会いのくだりのように色鮮やかな部分もあるけれど、だから素晴らしいというのではなくて、逆に、既存の研究の輪郭を明確にすることで、そこにある空白を際立たせてくれるからだ。もう本当に、余地の大きさのほうが印象的で、ちょっと読んだ自分まで思わず勇気づけられてしまうくらい。◇過去、あるいは遠くの場所での読書の姿との対照によって、当たり前に感じていることの当たり前じゃなさを浮き彫りにし、その可能性を広げる。読書が創造的な営みであることを改めて意識させてくれる。2014/09/20
スプリント
4
書物と読者の間に何が介在してそれが時代と共にどのような変遷を経てきたのか・・・読書という行為に対して多面的に考察をしている本です。アプローチが独特ですが非常に分かりやすい文章と構成になっているので読みやすかったです。2014/09/04
虎哲
2
読者に書物がいたる流れに書物が移動して読者に「たどりつくプロセス」と書物を読者が「理解するプロセス」があるとし、主に前者について書物の出版・流通史や検閲など実に多様な切り口・研究成果で論じている。「第9章読書と教育」と「第10章文学研究と読書」は国語科に大いに示唆を与える。例をあげれば、「「国語教育、国語科教科書に読書の歴史を組み込む」ということを、メディア・リテラシーを具体的に教育実践に移していく有効な方法として提案したい。」(223頁)がそれに当たるだろう。是非通読してその真の意義を検討して頂きたい。2019/02/27
-
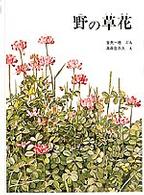
- 和書
- 野の草花 かがくのほん








