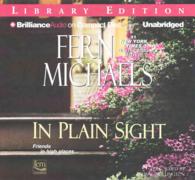内容説明
「女房」「召人」「後見」「乳母」…。侍女の様々な表現から、背後にある時代の文化と社会を理解する。
目次
序 平安物語における侍女
第1部 侍女の諸相と表現の差異(『源氏物語』における光源氏と侍女の関係―「女房」「御達」「女ばら」の表現の差異;「大人」と「童」との境界―『落窪物語』「あこき」を中心に;“召人”と『和泉式部日記(物語)』の女の差異)
第2部 侍女による「後見」(平安文学における侍女の「後見」の立場と展開;紫の上幼少期における少納言の乳母の「後見」―『落窪物語』からの影響と『源氏物語』の独自性;『狭衣物語』における侍女の変容―「後見」の比較を通じて)
第3部 乳母と家族との関係性(物語における宮中の乳母―『うつほ物語』今上帝の乳母を中心に;『源氏物語』における乳母一族の系譜―大弐の乳母、惟光、藤典侍から六の君へ;母親と乳母の関係―浮舟の母・中将の君と浮舟の乳母)
第4部 乳母子の役割と活躍(平安時代における乳母子の語義―『延喜式』・古辞書・『源氏物語』の分析から;『源氏物語』における夕顔の乳母子たち―系図の乱れと乳母子の役割について;宇治十帖の二人の右近―同名の侍女の近侍による錯覚)
宇治十帖における弁の君の立場―柏木の「乳母子」/大君・中の君の「後見」として
著者等紹介
古田正幸[フルタマサユキ]
1981年埼玉県生まれ。2012年東洋大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。2014年現在、東洋大学非常勤講師。平安朝文学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。