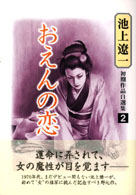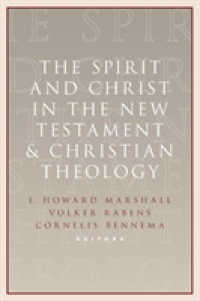内容説明
源平の武将たちが貴族の間で政治的駆け引きを行うためには和歌は必要不可欠な知識であり、御家人を統治するための手段となった。武士とは何か。和歌とは何か。源平の武将たちが遺した和歌を通して、貴族から武士への時代の転換点を探る画期的な書。
目次
中々に言ひも放たで(源頼光)
木の葉散る宿は聞き分く(源頼実)
夏山の楢の葉そよぐ(源頼綱)
吹く風をなこその関と(源義家)
思ふとはつみ知らせてき(源仲正)
もろともに見し人もなき(同)
有明の月も明石の(平忠盛)
うれしとも中々なれば(同)
思ひきや雲居の月を(同)
またも来ん秋を待つべき(同)〔ほか〕
著者等紹介
上宇都ゆりほ[カミウトユリホ]
1968年大阪府生。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科(博士課程)単位取得満期退学。現在、聖学院大学非常勤講師。主要論文「藤原定家考―天才形成の構造―」(新宮一成共著、日本病跡学雑誌)日本病跡学会奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。