出版社内容情報
うたの森に、ようこそ。
柿本人麻呂から寺山修司、塚本邦雄まで、日本の代表的歌人の秀歌そのものを、堪能できるように編んだ、初めてのアンソロジー、全六〇冊。「コレクション日本歌人選」の第2期第1回配本、永福門院です。
内容説明
その代表作を厳選して紹介。各歌には現代語訳をつける。振り仮名つきで読みやすい丁寧な解説つき。歌人略伝・略年譜を付し、生い立ち・歴史的背景がわかるようにした。より深く知るための読書案内付き。解説で、特色と、文学史的位置づけを行う。巻末に作家・評論家・研究者による名エッセイを収録。
目次
昔よりいく情けをか
薄霧のはるる朝けの
おのづから氷り残れる
なほ冴ゆる嵐は雪を
峰の霞麓の草の
木々の心花近からし
山もとの鳥の声声
入相の声する山の
うすみどりまじる棟の
風にきき雲にながむる〔ほか〕
著者等紹介
小林守[コバヤシマモル]
1943年東京都生。明治大学大学院修士課程修了。元明治大学文学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
102
永福門院は鎌倉時代の女性で、京極派の歌人だった。彼女の歌は、式子内親王のような新古今和歌集の女流の歌人とは明らかに異なる、特長を持っている。それは清新さと率直さで、歌自体が明るくて澄んだ印象を与える。歌の中にこの歌人の存在自体を感じられる。自然と向き合うこの歌人の姿が見えてくるようなところがあり、共感しやすかった。「月かげは森の梢にかたぶきて薄雪白し有明の庭」の美しい歌を読むと、雑念が洗い流されて心の中に清々しい風が吹き抜けていくような心地がする。(続きます)2017/12/12
しゅてふぁん
51
伏見院の中宮で京極派の代表歌人。私の永福門院の歌に対する第一印象は‘シンプル’だ。とにかく分かり易い。見たまま感じたままを三十一文字の歌に詠み込むのは難しいだろうに、それをさらさらっと詠んでいるように感じる。これだけの歌を詠むには繊細な心と鋭い観察眼が必要なんだろうな。繊細で新鮮な独自の感覚…どことなく清少納言と似ている気がする。お気に入りの歌は『空清く月さしのぼる山の端(は)にとまりて消ゆる雲の一群(ひとむら)/玉葉集・秋下・643』⇒2018/12/17
しゅてふぁん
45
再読。彼女の自然詠は読むにつれて徐々に一枚の絵画が完成していくような、歌に詠まれた風景が立体的に浮かび上がってくるような感覚になる。3D和歌!(笑)対象を見つめ、それをありのままに写そうとしていく京極派の自然詠は素晴らしい。永福門院は夕暮れを、夫の伏見院は雨を詠った作品が多い印象。この本の収録歌がそうなのか、それとも本人が好んだのか…玉葉集、風雅集を読んでみないとなぁ。2019/12/18
双海(ふたみ)
12
「その生と歌とは、七百年の歳月の彼方から、五月の薫風のようなさわやかさをいきいきと現代に吹き通わせている。」(岩佐美代子)鎌倉時代後期の太政大臣西園寺実兼の娘で、伏見院の中宮。院号を宣下される。両統迭立の時代に、持明院統の中心として生きて伏見院の志をつぐ。歌道は伏見院近臣の京極為兼を師とし、反二条派の歌風である京極派和歌をもっともよく体現した歌を残した。2024/03/10
サチ
0
図書館で借り読み。レポートのために。2019/07/06
-
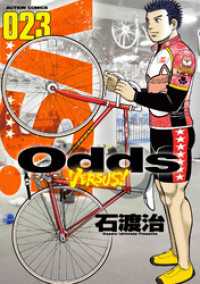
- 電子書籍
- Odds VS!(23) アクションコ…
-

- 和書
- 法人税法 - 実務と理論







