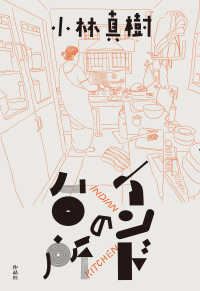内容説明
現在残されている板本や稿本から創作過程を細かく辿り、そこから馬琴作品に多く見られる手法を探ったり、潜在意識にある発想の型を見出す。そこから馬琴の目指した「娯楽としての読書」がどのように存在しえたかを考え、読書史の中で馬琴が果たした役割を考察する。
目次
第1章 馬琴合巻―化政期合巻と役者似顔絵(化政期合巻の世界―馬琴合巻と役者似顔絵;馬琴著作の稿本に見る「役者」と「役柄」;馬琴合巻における似顔絵使用役者一覧)
第2章 馬琴読本―板本と稿本から見た物語の創造(『占夢南柯後記』;『南総里見八犬伝』)
第3章 馬琴戯作の原型―想像力の基底と瀧澤家(馬琴戯作における想像力の原型―馬琴と「小夜の中山」伝説;瀧澤家の人々―女性たちをめぐって 「『吾仏の記』から」)
第4章 戯作の読者と読書―草双紙と浮世絵(草双紙の読者―婦幼の表すもの;楚満人と馬琴―草双紙におけるヒロイン像の変遷;浮世絵における女性読者像の変遷)
著者等紹介
板坂則子[イタサカノリコ]
1952年生まれ。東京大学大学院博士課程修了。群馬大学教育学部専任講師、助教授を経て、専修大学文学部教授。専攻は日本近世文学文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。