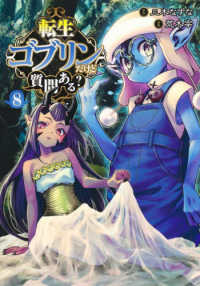出版社内容情報
江戸初頭から明治期まで、形を変えながらも作られ続けた、
笑話の抄録本という性質を持つ噺本。
大局的な分類から一歩進め、噺本の価値と特質を明らかにする。
作者、板元は誰だったのか。
江戸戯作出版メディアの一端を解明する。
話芸を文芸化するとは、どういうことだったのか。
従来看過されてきた噺本の近世文学史上における価値について、改めて論究しつつ、
近世中期文芸の担い手として他の文芸にまたがった活躍をみせた
噺本作者たちの実体解明の端緒となることが本書の目的である。
まえがき
凡例
第1部 咄本の作り手達
第一章 江戸小咄本の作り手
一節 『口拍子』シリーズの作り手達
二節 『飛談語』シリーズの作り手達
第二章 軽口本の作り手
一節 舌耕者の軽口本、非舌耕者の軽口本
二節 雑俳師の軽口本
三節 軽口本から『鹿の子餅』へ
第2部 噺本における「咄」の諸相
第一章 言葉の洒落のはたらき
第二章 話し手の存在
第三章 雅文笑話集の位置付け
第3部 噺本、表現の可能性 その視覚的効果
第一章 仕形咄本
第二章 絵咄本
第三章 軽口本の表現
第四章 咄本における絵の機能
第4部 資料編
第一章 『古今諸家人物志』諸本研究
第二章 『老翁談』 翻刻と紹介
付章 噺本の古典教材化への試み
資料出典一覧・論文初出一覧・索引[書名・人名]・あとがき
内容説明
江戸初頭から明治期まで、形を変えながらも作られ続けた、笑話の抄録本という性質を持つ噺本。大局的分類から一歩を進め、噺本の価値と特質を明らかにする。
目次
第1部 噺本の作り手達(江戸小咄本の作り手;軽口本の作り手)
第2部 噺本における「咄」の諸相(言葉の洒落のはたらき;話し手の存在 ほか)
第3部 噺本、表現の可能性―その視覚的効果(仕形咄本;絵咄本 ほか)
第4部 資料編(『古今諸家人物志』諸本研究;『老翁談』―翻刻と紹介)
著者等紹介
鈴木久美[スズキクミ]
1972年静岡生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(学術)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 剣は知っていた(下)
-

- 和書
- クイックマスターin簿記