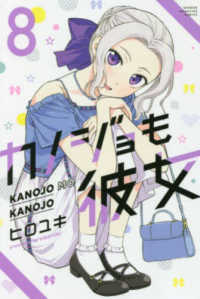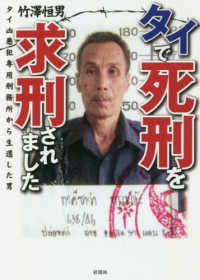出版社内容情報
『源氏物語』の文脈に深く関わる音楽。
その理解なくして源氏の真の解釈は成立しない。
当時の音楽理解のためには物語文脈を一旦離れ、
音楽史の上に作品を置いてみることである。
本書は、これまで斯界の陥っていた安易な推論を払拭しようと、
物語成立前後から中世にかけての文献を用いて、
より実証的な解釈に迫っていこうとするものである。
平安時代の宮廷音楽はどのようなものであったのか。
緒言
序に代えて 狛氏幻想--南山城の古代より--
第一部 『源氏物語』の音楽研究にむけて
一 『源氏物語』と音楽--中世の楽書から--
二 「兵衛命婦」考--『源氏物語』の音楽研究にむけて--
三 『源氏物語奥入』に見える楽人、多久行について
四 「詠」について--序説--
五 舞楽における歌唱の終焉について--「詠」と「囀」の変容--
六 「舞ノ行道」考--舞の家、多氏の言談について--
七 『枕草子』の音楽表現
--「奈良方」と「法華八講」を中心に--
八 『文机談』--聞き手「中河のほとりの尼」の造形について--
第二部 『古事談』の音楽説話から
一 『日本三代実録』巻頭について--「童謡」考--
二 「臨時祭」考--『古事談』第一--第三十話より--
三 斉信が公任に代って御神楽の拍子を取ったこと
--『古事談』の音楽説話小考、巻第一--第四十六話より--
四 『古事談』巻第一--第四十九話を読む
--「内侍所御神楽」成立考--
附 中世文学と相承
--南都における学芸、音楽、説話方面より--
第三部 楽書の研究
一 『管絃音義』における『白虎通義』の影響
--『管絃音義』の引用について--
二 「蘇合四帖」考
--『胡琴教録』上より、管絃曲《蘇合》について--
附『源氏物語』音楽表現一覧ノート
出典一覧/結び/索引
内容説明
当時の音楽理解のためには物語文脈を一旦離れ、音楽史の上に作品を置いてみることである。本書は、これまで斯界の陥っていた安易な推論を払拭しようと、物語成立前後から中世にかけての文献を用いて、より実証的な解釈に迫っていこうとするものである。
目次
狛氏幻想―南山城の古代より
第1部 『源氏物語』の音楽研究にむけて(『源氏物語』と音楽―中世の楽書から;「兵衛命婦」考―『源氏物語』の音楽研究にむけて;『源氏物語奥入』に見える楽人、多久行について ほか)
第2部 『古事談』の音楽説話から(『日本三代実録』巻頭について―「童謡」考;「臨時祭」考―『古事談』第一‐第三十話より;斉信が公任に代って御神楽の拍子を取ったこと―『古事談』の音楽説話小考、巻第一‐第四十六話より ほか)
第3部 楽書の研究(『管絃音義』における『白虎通義』の影響―『管絃音義』の引用について;「蘇合四帖」考―『胡琴教録』上より、管絃曲「蘇合」について)
附 『源氏物語』音楽表現一覧ノート
著者等紹介
磯水絵[イソミズエ]
1950年東京生まれ。1969年東京都立三鷹高等学校卒業。二松學舎大学入学。1978年二松學舎大学大学院満期退学。二松學舎大学文学部助手となる。1994年専任講師、助教授を経て国文学科教授。2001年博士(文学)乙取得(二松學舎大学)。専攻は中世文学、説話文学、日本音楽史学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 失恋したのでVtuberはじめたら年上…