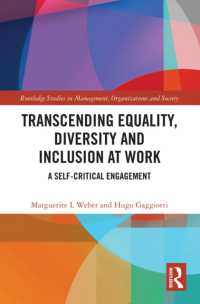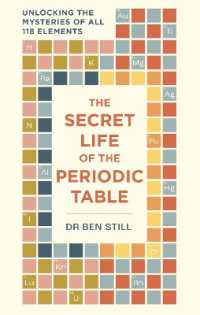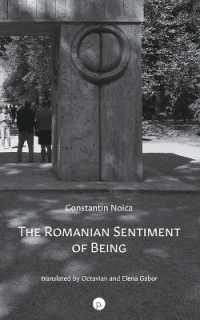目次
第1章 論点
第2章 起源
第3章 現状
第4章 Safety‐1の神話
第5章 Safety‐1の脱構築
第6章 変化の必要性
第7章 Safety‐2を構築する
第8章 進むべき道
第9章 最終の考察
著者等紹介
北村正晴[キタムラマサハル]
1942年生まれ。東北大学大学院工学研究科原子核工学専攻博士後期課程修了。工学博士。同大学助手、助教授を経て1992年東北大学工学部原子核工学科教授、2000年同研究科技術社会システム専攻リスク評価・管理学分野を担当。2005年定年退職、東北大学名誉教授。現在(株)テムス研究所代表取締役所長。専門は、技術システムの安全性向上、大規模システムにおける人間・機械の協調、原子力技術に対する社会の受容性等
小松原明哲[コマツバラアキノリ]
1957年生まれ。早稲田大学理工学部工業経営学科、同大学院博士後期課程修了。博士(工学)。金沢工業大学講師、助教授、教授を経て、2004年4月から早稲田大学理工学術院創造理工学部経営システム工学科教授。専門は人間生活工学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
閑居
9
Safety1は失敗の極小化、受動的対策、失敗と機能不全に依拠する事故分析。Safety2は成功の極大化、能動的対策、結果に依存しない因果分析。Hale,Hovdenは1979(スリーマイル原発事故)までをFMECA等でシステミックに対策する技術の時代、1979~2000までをヒューマンエラーを対策する人的要因の時代、1986年(チャレンジャー号、チェルノブイリ)以降を組織を対策する安全マネジメントの時代、と区分した。2022/08/11
Yasutaka Nishimoto
0
医療安全の学会で紹介されていて、情報がある状態で読んだ。「それでは今までやっていたことは何だったんだ?」ではなくて、「Safety1と並立させつつSafety2を」ということなので徐々に移行していけば良いかとは思う。ただ、組織の幹部は早急に目を通した方がよく、その概念だけでも押さえておかないと、現場の方法であっぷあっぷになりながら時間を浪費することになると予想されるため、最低限、前向きな事故報告書が出てくる状態だけは確立させるよう努める必要がある。著者の「レジリエント・ヘルスケア」を読みたいが、高い…。2016/11/21
Kazuyuki Koishikawa
0
失敗をなくすんじゃなくて、うまく行くことを増やすという考えが面白い。2016/11/05