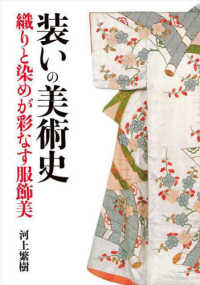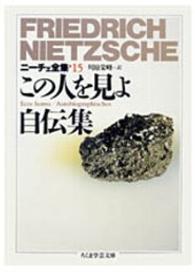出版社内容情報
ベストセラー『80歳の壁』の和田秀樹氏による「不機嫌のトリセツ」。社会保障も年金もあてにできない老後を生き抜くために最も重要な能力は「人から嫌われない」こと。助けてくれる友人、家族、知人の存在こそが最大のセーフティネット、生きるよすがとなる。私たちの老後の暮らしの質を左右するのは「不機嫌という病」の克服。これこそが、最も優先度の高い「老後の備え」「最強の貯蓄」だ。
内容説明
1匹の妖怪が日本を徘徊している。不機嫌という名の妖怪が―。電車の中で咳き込めば苛立ちの視線の嵐。SNSは批判とマウントの格闘場。「地獄とは他人のこと」と言ったのはサルトルだが、まさに「他人」は地獄、日本社会は地獄だらけといった様相だ。しかし、私たちは「地獄」だからといって「他人」との関係を断絶して生きることはできない。人口減少、賃金停滞、年金崩壊…日本が地盤沈下していく今、むしろ周囲の人とのつながりこそ最重要な「資本」になる。和田秀樹的「シン・幸福論」!
目次
第1章 不機嫌の正体(大きな正義を振りかざす人で溢れている;不機嫌な人は二分割思考にとらわれている ほか)
第2章 不機嫌な人の行動パターン(同調することで共同体から弾かれまいとする;なぜマスクを外せないのか ほか)
第3章 不機嫌を生む日本社会の病理(他者への共感には健全な自己愛が不可欠;子どもへの愛ではなく自己愛ゆえに暴走する親たち ほか)
第4章 不機嫌との付き合い方(不機嫌な気持ちは放っておく;感情を発散させるのに有効な「鍵アカウント」活用法 ほか)
第5章 機嫌がいい人ほど人生はうまくいく(人生の幸せを左右するのはお金よりもソーシャルキャピタル;機嫌のよさとソーシャルキャピタルの豊かさは比例関係 ほか)
著者等紹介
和田秀樹[ワダヒデキ]
1960年、大阪府生まれ。精神科医。ルネクリニック東京院院長。東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、浴風会病院精神科医師を経て現職。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひらちゃん
テツ
門哉 彗遙
ちい
TT
-
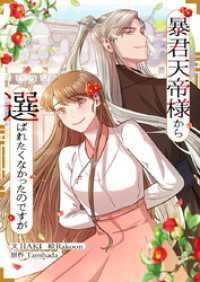
- 電子書籍
- 暴君天帝様から選ばれたくなかったのです…
-
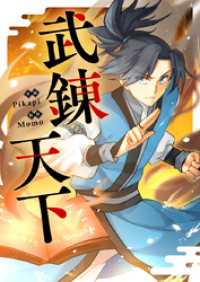
- 電子書籍
- 武錬天下【タテヨミ】第39話 picc…