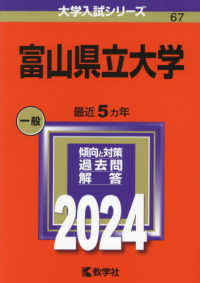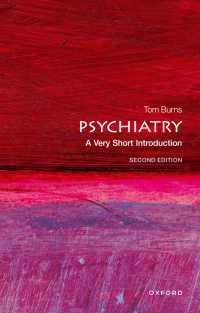出版社内容情報
GitHub CopilotやChatGPTなど生成AIによるコード生成やコードリーデイング支援が流行っています。
これらは破壊的なイノベーションで、いずれはすべての開発者や企業が導入するものです。
ただ、現状では生成AI×コードを推進・導入している企業は多くはなく、さらに活用法については手探りの状況です。
本書では生成AI×コードでなにができるか、どうすればよりよく活用できるかを解説します。
しっかりと活用していくための知識と、現場で活用できる実践が身に付く必携の一冊です。
内容説明
ChatGPTやGitHub Copilotに代表される生成AIの躍進はソフトウェア開発を一変させた。AIとともに進めるコーディング、コードリーディング、ドキュメンテーション、要件定義、設計、レビュー。新時代の必須スキルを習得する。
目次
第1章 生成AIがエンジニアリングの常識を変える
第2章 プロンプトで生成AIを操る
第3章 プロンプトの実例と分析
第4章 AIツールに合わせたプロンプト戦略
第5章 AIと協働するためのコーディングテクニック
第6章 AIの力を引き出す開発アプローチ
第7章 生成AIの力を組織で最大限に引き出す
第8章 開発におけるAI活用Tips
第9章 AI時代をリードするために
Appendix Practice Guide
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tyfk
4
開発組織戦略などは他書にない視点か。それにしても全体的に文章がくどい、生成AIで下書きしたんだろうな2025/06/10
monotony
4
生成AIをソフトウェア開発で使うためのプラクティス集。AIと人間の協調という点に重きを置いているような印象でした。2024年10月発刊の本のため、それ以降の発展、特にエージェント型AIについての言及は多くはなかったが、その土台になるものは得られると思います。最後第9章の内容も良かったです。2025/05/12
おい
2
★★★2025/07/07
蠍
2
全体的に間違いないことを書いている分、驚くような内容はなかったが、だからこそ地に足ついている感じがした。 個人的には図が欲しいのだが、全然なかった。 この本自体が生成AI使って書かれているので、AIが苦手だと思われる図の作成はしてなかったのかなと感じた。(テキストのまとめのテーブルみたいなのはあった) AIはリーンなコードが好きというのを全体を通して感じ、だからこそMarkdownが好きなのだと思った。#terminalLastCommandなどWEB系の開発では使いやすいんだろうなという印象ができた。2024/12/07
Kazuyuki Koishikawa
2
使い方のヒントとか得られてよかった。2024/11/12