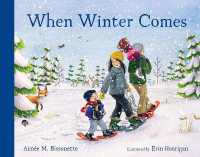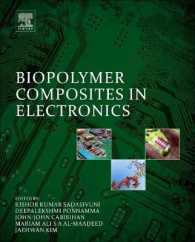出版社内容情報
100年間誰も疑わなかった「地形学の常識」に地質学者が挑む、第2弾!!
「準平原」とは、地表が長期にわたる侵食作用を受けて起伏が小さくなり、海面の高さ付近まで低下した、ほとんど平らな地形のこと(国土交通省東北地方整備局HPより)。
アメリカの地形学者ウィリアム・モーリス・デービスが100年以上も前に提唱した侵食輪廻説における最末期の地形で、地殻変動(隆起運動)が停止後、河川による侵食によって海面付近まで低くなった起伏の小さいなだらかな平原を指す概念です。
重要な点は、「準平原は陸上で河川によってつくられた地形である」と述べていることです。
日本列島には、標高の異なる起伏の小さい侵食小起伏面が知られています。
とりわけ、中国地方にはかなりの広がりをもつ明瞭な侵食小起伏面が数段あり、それらはアメリカの地形学者デービスが提唱した「準平原が隆起したもの(隆起準平原)」であるとずっと信じられてきました。
ところが、前著『分水嶺の謎 峠は海から生まれた』で考察したように、谷中分水界や片峠は、島と島の間の海峡が離水した地形でした。
それらが標高1000mを超す山地にも確認されることから、かつての海峡(海底)が大きく隆起していることを意味します。
中国地方の隆起準平原とされた地形を丹念に観察すると、平坦な地形はいずれも起伏の少ない分水界に囲まれていて、分水界には谷中分水界や片峠が確認されます。
ということは、谷中分水界や片峠が海峡だったころ、分水界に囲まれている起伏の小さい地形は……浅い海底だったのではないでしょうか。
デービスが提唱した
「準平原は陸上で河川によってつくられた地形である」
という考え方は、本当に正しいのでしょうか?
本書は、100年近く信じられてきた本邦地形学の常識(隆起準平原)を見つめ直し、谷中分水界や片峠を鍵として、その成り立ちの謎について解いていきます。
内容説明
隆起準平原と信じられてきた中国地方の吉備高原。吉備高原より一段低い、真っ平らな世羅台地。さらに低い、瀬戸内面の侵食小起伏地形。デービスが提唱した侵食輪廻説の終末期の地形『準平原』は、本当に存在しているのだろうか?100年を超す地形学の常識を疑い、新たな視点で地形の謎をひもとく第2弾!
目次
旅の準備
第1日 思い出の場所で“鍵”のチェック
第2日 “鍵”を閉じれば背中合わせの盆地
第3日 海が削った吉備高原
第4日 海面は海底と陸地の間の関所
第5日 水にとってはすべてが盆地
第6日 4次元地形学への誘い
第7日 私が地形に夢中な理由
第8日 高所に残る海の痕跡
第9日 川を下ればタイムトラベル
著者等紹介
高橋雅紀[タカハシマサキ]
1962年、群馬県前橋市生まれ。1990年に東北大学大学院理学研究科博士課程を修了後、日本学術振興会特別研究員および科学技術特別研究員を経たのち、1992年に通商産業省(現経済産業省)工業技術院地質調査所(現産総研)に入所。専門は地質学、テクトニクス、層序学。大学の卒業研究以来、関東地方の地質を調べ日本列島の成り立ちを研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MASA123
mft
とりもり
Hiroki Nishizumi
しぇるぱ
-
- 洋書
- Rumer